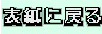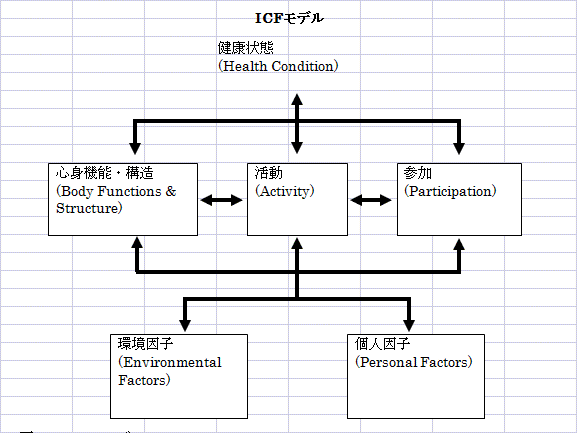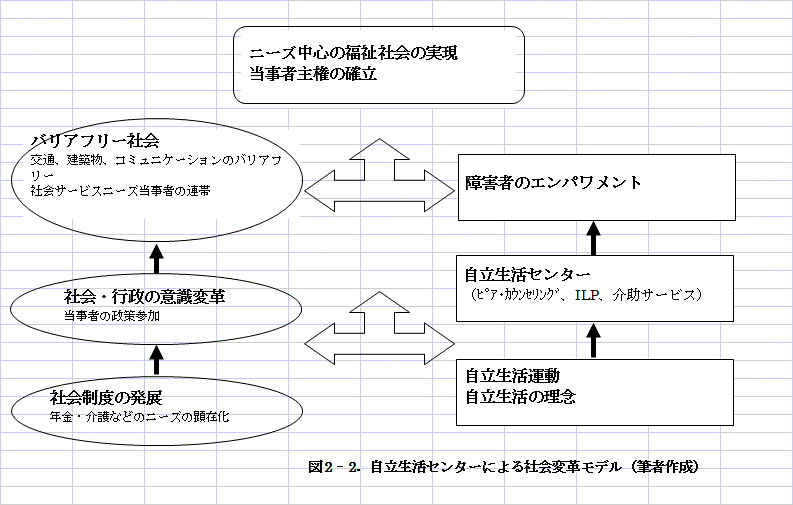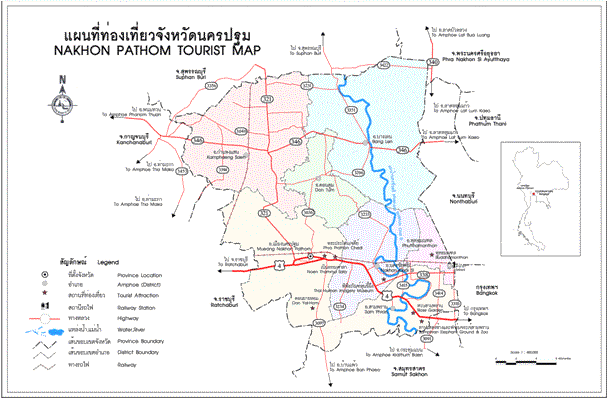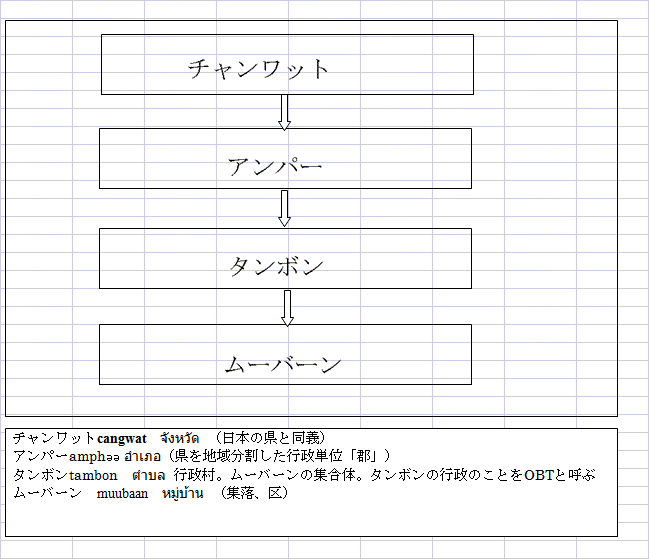途上国の自立生活センターによる重度障害者のエンパワメントと社会変革 ― タイ・ナコンパトム県自立生活センターの設立過程とその成果の分析
日本福祉大学大学院国際社会開発研究科国際社会開発専攻修士課程
中西正司
2009年度卒業論文
修士論文目次
第1章 研究の目的と意義
第1節 問題の所在 3
第2節 研究の目的 3
第3節 研究方法 3
第4節 研究の意義 4
第5節 論文の構成 4
第2章 自立生活センターの理念と本研究の枠組み
第1節 自立生活の定義 6
第2節 医療モデルから社会モデルへ 7
第3節 自立生活センターの目的 9
第4節 自立生活センターのサービス 10
第5節 自立生活センターの運動 13
第6節 途上国の自立生活センターに関する先行研究 13
第7節 自立生活センター成立の5指標 15
第8節 障害当事者と社会変革をめぐる先行研究 20
第9節 仮説の設定 21
第3章 タイの自立生活センターの事例研究
第1節 タイにおける障害者のおかれた状況 24
第2節 ナコンパトム県の概況 27
第3節 調査対象 28
第4節 調査方法 30
第4章 ナコンパトム自立生活センターの設立と展開
第1節 ナコンパトム自立生活センターの設立過程 35
第2節 ナコンパトム自立生活センターを自立生活センターたらしめた要因 36
第5章 障害者のエンパワメントと社会変革
第1節 ナコンパトム自立生活センターの障害者のエンパワメントについて 50
第2節 ナコンパトム自立生活センターはいかに行政と社会を変えているか 53
第6章 考察と結論
第1節 ナコンパトム自立生活センターの相対的独自性について 56
第2節 今後の課題 59
参考文献 60
第1章 研究の目的と意義
第1節 問題の所在
アジアにおいて重度障害者はいまだに施設か親元で居住する者が多く、行政のサービスも障害者の地域居住を支えるものとはなっていない。重度障害者は保護と管理の中で自己選択や自己決定の機会を奪われ、依存と自己尊厳を否定される状況におかれている。
先進国においても1970年代以前には同じような状況が見られた。これを変えたのが1970年代に生まれた「自立生活」の理念である。この理念はそれまで社会で無視されてきた重度障害者に希望の光を与えた。障害者自身の自己選択・自己決定を基本に据えて、地域で障害者が障害者を支援する自立生活センターはとくに重度障害者を対象としている。彼らが地域で居住することは、年金、介助、交通アクセス、教育、就労などあらゆる社会的ニーズが顕在化することにつながり、行政に社会福祉制度の大幅な変更をせまることになる。ピア・カウンセリングなどのツールによって自らをエンパワーし、自己尊厳をとりもどした障害者は、障害の原因は自らの身体機能にはなく、社会の福祉制度や建築、交通のアクセスなどにあることに気付き、自立生活センターを核として地域を変え、行政を変え、社会を変えていく。これが自立生活センターの意義である。
そこで、先進国では社会の変革ツールとして機能した自立生活センターが、文化や経済背景が異なる途上国でも可能であり、社会変革として機能しうるかどうかが、途上国での大きな課題となる。本論文は、筆者自身が自立生活運動をアジアで推進してきた当事者として、タイ・ナコンパトム県の自立生活センターの発展過程を追いながら、この課題にとりくむものである。ナコンパトムで自立生活センターが社会変革のツールとして機能することが立証できれば、今後アジアの途上国で重度障害者が地域で自立生活をしていくための道筋を示せることになろう。
第2節 研究の目的
ナコンパトム自立生活センターを対象に、それが運営上自立生活センターの理念を満たして機能していることを検証し、さらにこの自立生活センターを基礎とした当事者エンパワメントが社会との相互関係の中で社会変革にどのようにつながっているかを明らかにする。かくして今後アジアで自立生活センターを展開させるための根拠を示すことが、本論文の目的である。
第3節 研究方法
本研究の中心は、自立生活センター普及活動を進める筆者自身の当事性を明らかにした上での、タイの当事者・関係者へのインタビューである。ナコンパトムの自立生活センターで、運営責任者、職員、介助者、利用者から、自立生活センターの設立経過と、活動内容、自立生活センターの提供するサービスの現状を現地での通訳を交えての聞き取りを通じて調べる。また、ナコンパトムの自立生活センターが当事者をいかにエンパワメントし、社会を変えていっているかを調べる。この際に、調査の客観性を強めるために、行政の担当者、近所の住民、家族の面接調査を行って、上記の聞き取り内容と照合する。
第4節 研究の意義
重度障害者のニーズに基づいた自立生活センターは先進国においてのみ可能なシステムだという批判があるが、途上国であるタイの地域においても障害当事者のエンパワメントが可能であり、自立生活センターを組織することで社会を変えていくような運動が可能であることを学術的に立証できる。また重度障害者と地域福祉の相互発展過程を明らかにすることによって、アジア諸国の障害者の自立生活を可能にする福祉サービス制度の確立への方策が提示できるだろう。
開発分野において当事者による当事者に対する支援が有効であることは近年言われてきたが(久野・中西 2004)、具体的な事例に乏しかった感は否めない。この論文は開発における当事者参加を具体的に行っている例として、ピア・カウンセリングや自立生活プログラムなどの当事者活動を障害当事者の視点から調査・分析・報告するもので、今後の開発論に新たな視点を加えることになるだろう。
第5節 論文の構成
第1章では、本論文の目的と意義を述べた。途上国ではいまだに重度障害者は、施設や親元の保護と管理のなかで主体性を持てないでいる。一方、先進国では重度障害者は、自立生活センターの支援を受けて自己選択・自己決定のもとでくらし始めている。途上国のタイで自立生活センターが可能かどうかをナコンパトムの事例で確認することが本稿の目的であり、それは今後アジアの開発途上国で自立生活センターによって、重度障害者の生活を変えることができることにつながり、大きな意義があることを述べた。
第2章では、第1節で自立生活について独自の定義を定め、先行文献によりその理由を明らかにした。第2節では自立生活運動を理論的に支える「社会モデル」の説明をし、第3節で自立生活センターの本来目指す「個の変革」と「社会変革」という目的をあきらかにした。第4節で変革へのツールとして自立生活センターが開発したサービスであるピア・カウンセリング、自立生活プログラム、介助サービスについてそれぞれの内容と目指すところを示した。自立生活センターのサービスと並んで両輪を成すのが運動である。第5節では自立生活センターの運動体としての側面について、「個人アドボカシー」と「システムアドボカシー」があることを説明した。第6節では途上国の自立生活センターの先行研究からいままでどこまでが語られどこからが述べられてないかをあきらかにした。第7節では自立生活センターが成立しているかどうかを判定する指標として5指標をあげ、その意味するところを詳しく説明した。第8節では障害当事者と社会変革を巡る先行研究としてフレイレの「課題提起型アプローチ」をとりあげ、その「対話型」の本質が自立生活センターで使われるピア・カウンセリングのなかでの対等な関係での対応による相互変革過程と似通っていることを指摘し、理論的な研究の分析ツールとしてフレイレの「対話」「意識化」「社会変革」の3指標を得た。第9節ではこれまでの論述をふまえて、「途上国でも自立生活センターは成立しうる。そして、それを基盤として当事者をエンパワーし、そのニーズを顕在化させ社会変革ができる」という仮説をたてた。
第3章では、まず第1節でタイにおける障害者のおかれた一般的な状況についてデータに基づいて説明し、第2節で研究対象地域であるナコンパトム市の概況を示した。第3節ではタイに7つある自立生活センターのうちで、なぜ本論文ではナコンパトム自立生活センターを選んだか、その根拠を示した。第4節では現地調査の日程と調査方法、面接調査対象とその方法などを述べ、とくに実証的データをバイアスのかからないように集めるために留意した点を記した。
第4章では、第1節でナコンパトム自立生活センター設立過程を聞き取り調査と既存資料から示した。第2節では、この設立過程についての調査データを上記5つの指標に照らして調べ、同センターが「自立生活センター」といえる内容になっていることを確認した。これら5指標がどのような過程を通じて達成されるにいたったかが、本章の関心である。
第5章では、本研究の仮説の後半「自立生活センターが障害者をエンパワメントし、そのニーズを顕在化させて社会変革につながる」かどうかについて、考察している。第1節では、ナコンパトム自立生活センターが障害者をエンパワーしていることを検証した。また第2節では、エンパワーされた障害者によって社会変革がはじまり、障害者のニーズが顕在化して福祉サービスが向上したことを明らかにした。
第6章1節では、途上国では自立生活センターが難しいと言われているのになぜナコンパトムでは成立したのか、またタイの他の2つの自立生活センターと比較してナコンパトムのセンターだけが成功しているといえる理由はなにかについて考察した。第2節では本論文で触れることのできなかった今後の課題について述べた。
第2章 自立生活センターの理念と本研究の枠組み
第1節 自立生活の定義
筆者は、「障害者の自立生活」とは「障害者が人生の主体として、社会の中で自己選択・自己決定し、介助などの支援を得ながら地域で平等な機会を与えられて、普通の生活を送ること」と考える。その根拠を以下に示す。
一般に言われる「自立(Independence)」は、ロングマン英英辞典によると "the freedom and
ability to make your own decisions and take care of yourself,
without having to ask other people for permission, help, or money"(他の人たちからの許可や支援、資金を受けることなく、自らを自足し、自己決定を行う自由と能力)として、また広辞苑では「他の援助や支配を受けず自分の力で身を立てること。ひとりだち」と定義されている。
1972年、自立生活運動(Independent Living Movement)の創始者であるEd Robertsは、自己選択、自己決定をすること、自分で全ての自己ケアをして社会参加できないよりも、介助や支援を得て社会参加すること選ぶことが「自立」であると定義した。
DeJongは「リハビリテーション」と「自立生活」を二つのパラダイムとして対比させて表にまとめている。
表2-1「リハビリテーションと自立生活パラダイムとの比較表」
|
リハビリテーションのパラダイム |
自立生活のパラダイム |
| 障害の定義 |
身体的欠損、職業的技能の欠如 |
専門家、家族への依存 |
| 問題の所在 |
個人の中 |
環境、リハビリテーションの過程 |
| 問題の解決 |
専門家の介入(医者、PT、OT、職業リハカウンセラー) |
ピア・カウンセリング、権利擁護、自助活動、消費者コントロール、障壁の除去 |
| 社会的役割 |
病人、患者 |
消費者 |
| コントロールする者 |
専門家 |
消費者 |
| 求められる結果 |
ADLの最大化、有利な雇用 |
自立生活 |
出展:Greben DeJong, "Independent Living: From Social
Movement to Analytic Paradigm," Arch phys Med Rehabil, vol.
60, (October 1979), p.443.
前者においては障害「問題」のありかが身体的欠損、職業技能の欠如にあると定義されるが、後者では「問題」は専門家や家族への依存にあると定義される。障害者の生活を管理するのは、前者では専門家であるが、後者では必要なサービスを自ら選択する「消費者」としての当事者である。したがって「問題解決」の手段となるのは、前者では専門家による医療やリハビリであるが、後者の枠組みではピア・カウンセリングや権利擁護、自助活動、障壁の除去などがあげられる。
Lex Friedenは自己決定を重視し、「自立生活用語集」の中で、「自分の人生を自分でコントロールすること。決断をくだしたり、毎日の生活を営む上で自分の望むところを選択し、他の人に対する依存を最小限にする。・・・地域の毎日の生活に参加すること、社会的な役割を担うこと、・・」(Frieden
1979(中西 1991, p.5にて引用))と自立生活を定義している。ここではさらに、自分の人生の主体者であること、地域での社会参加や社会的な役割を果たすことが強調されている。また立岩真也は『生の技法』の中で、「自立生活とは、そこに込められている独立・自律への希求を具体化した生活の形として、日常的に介助=手助けを必要とする障害者が、『親の家庭や施設を出て、地域で生活すること』である。」と規定している。この文脈の中で立岩は、自立生活を「重度障害者が介助を受けて、地域で暮らすこと」(立岩1995,
p.1)に焦点をあわせて述べている。このように自立の意味がリハビリテーションが唱えていたものとは、根本的に変遷してきたことが分る。
しかしながら、これらの要素とともに、自立生活運動の現場から見た現時点における状況の変化を踏まえて、「地域で平等な機会が与えられる」という要素も「障害者の自立」の概念に付け加えたい。その理由は、社会参加していくためには教育、就労、交通機関、建築上のアクセス、社会の障害者の受け入れ体制などの環境の整備などの、機会の保障が充分にされることが必要であるためである。
Sen(Sen 1999, p.25, 210, 233)は、福祉の基準となるのは、富や所得のような手段でなく、また幸福といった主観的結果や効用でもなく、多様な生き方を実質的に可能とする選択肢の広がり(「ケイパビリティ」)であるとしている。そこでは、形式的な「機会の平等」ではなく、ある人が自ら価値あるとする生き方を実際に実現できるための社会的条件がどれだけ整えられているか、その機会集合の大きさこそが問題である。筆者の言う機会の平等とは、Senが唱えているように、機会集合の最大化が個々人になされることが前提となる。
以上の考察により、筆者は「自立」について冒頭の定義を得た。
第2節 医療モデルから社会モデルへ
1960年代のリハビリテーションでは、障害は身体機能の欠損とみられ、障害者は努力をして機能を回復して健常者に戻ることが求められた。しかし、この考え方では、重度の障害者は一生施設から出られなくなる。
1970年代に現れた自立生活センターでは、障害は環境が作り上げるものという考え方をする。障害者を受け入れるアクセシブルな交通機関、建物と日常生活や移動を支援してくれる介助者がいる社会を作り上げることで、重度障害者も地域で普通に暮らすことができるようになる。
1980年にWHOは「機能障害、能力障害および社会的不利の国際分類」ICIDH(International Classification
of Impairments, Disabilities, and Handicaps, 1980)を制定する。それによると病気や体の変調によって正常な状態からはずれるとその結果機能障害が起こり手足が動かなくなったり言語が話せなくなったりする。その機能障害は個人の能力の障害として表れてくる。つまり字が書けなかったり移動の障害が起こったりする。今度はその能力障害によって社会的な不利が生まれる。このように障害を個人のベースで見て、正常な状態から逸脱したものを障害と捉え、正常に戻すためにリハビリテーションが不可欠であるとする。リハビリテーションの目標は元の正常な人間に戻すことである。正常に戻らない障害者は一生リハビリテーションを続ける努力が義務付けられる。重度障害者は施設に収容されてきたのも、リハビリテーションの理念という支えがあったからである。
障害者団体からはリハビリテーションと施設を擁護する理論と見られたICIDHは評判がよくなく、WHOもその批判に応えてICIDHの見直しを図ることになる。新たな障害分類を開発するため今度は障害者団体にも声をかけ、世界各国でICIDH改訂のためのフィールドトライアルがICIDH-2(生活機能と障害の国際分類、International
Classification of Functioning and Disability, 1999)を使って行われた。日本においては上田敏会長のもとICIDH-2を使ってみて、それで障害が捉えられるかどうかを当事者を入れた委員会のなかで意見を出し合い検討した。その国内意見を取りまとめその結果をWHO本部に集めそれに基づいてマドリッドで2000年に開催されたWHOの年次国際改訂会議において最終調整が行われ、2001年WHO総会でICF(国際生活機能分類、International
Classification of Functioning)の名称に改められ成立した。
ICFでは障害の原因を社会に求める。個人の活動は本人の個人因子と環境因子、心身機能と健康状態、さらに社会参加の側面から制約を受けていると捉える。
障害は社会の中の環境である建物・階段やアクセス化がされていない電車やバスと障害者を受け入れない学校や職場など社会の側に原因があると捉えている。これらの社会の中のバリアや障害者に対する不当な差別や不利益を取り除いていくことによりその人の障害は軽減され社会参加活動の幅が広がってくる。このことに気付いた障害者たちは自らの発言や行動に自信を持ってあたるようになってきた。また家族や周囲の人たちも障害者をあからさまに差別できなくなったのもICFができてからである。これまで政府が障害者を施設に閉じ込めるのを当然としていた政策を翻し、施設から地域へと移動し始める支援費制度や介護保険制度などの改革に切り替えたのもICFができたおかげといえる。
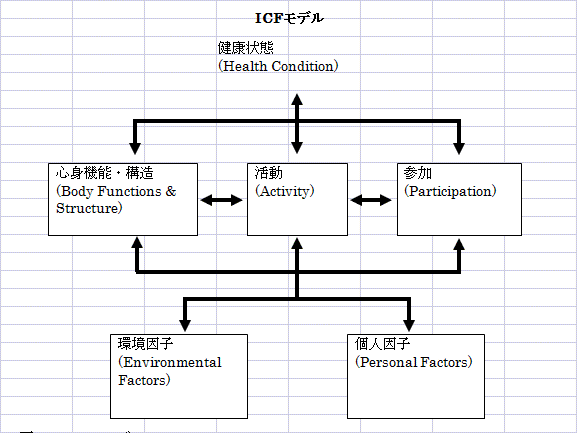
図2‐1.ICFモデル
出典:「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」(日本語版)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html に基づき作成
第3節 自立生活センターの目的
1970年代以前の日本において障害者は、施設や親元でその保護と管理のもとで暮らす以外に生きる方法はなかった。アジアにおいてはいまだに同様の状況が続いており、大家族制のもと家族が障害者の面倒をみるのが社会通念として当然のことと考えられており、障害者の面倒をみない家族は、社会から訴追を受ける怖れすらあるため、実質的には当事者の意向を押し殺しながらも、外見的には障害者に優しい家族として振舞っている。また施設では、保護と管理の名の下に、閉鎖的な環境の中で社会的経験を奪われ、自己決定権を奪われた生活を余儀なくされる。時には人権侵害も起こった。
このような状況を生み出す背景となる理念がリハビリテーションの理念であり、障害者は健常者の機能的な欠損を起こした状況にあり、リハビリテーションによってその機能を回復しもとの健常な身体に戻ることを求められ、一生にわたる訓練を課される。リハビリによってもとの健常な体に戻れない重度障害者にとっては、この理念は過酷であり、劣等なリハビリテーション対象者として分類され、リハビリ継続施設や障害者用入居施設に追い込まれる状況が、日本においても80年代にも続いており、アジアにおいてはいまだにその状況は変わっていない。
この状況の中で生まれたのが、1970年代にエド・ロバーツによって提唱された自立生活の理念である。エド・ロバーツは四肢麻痺であり、「食事を2時間かけて補助具を使って自分で食べるより、介助者に手伝ってもらって食べたほうが良い」と言った(1981年10月9日、第5回車いす市民全国集会(大阪)での発言から)。しかし、より世間に流布しているのは、「2時間かかり自分で着衣をするよりも、自己決定によって介助者に介助を頼み、その時間を社会参加に有効に活用することが良いことだ」と言うガーベン・デ・ジョング(De
Jong 1979) からの引用である。
ともかく自立生活の理念が彼らによって提唱されたということは大きな意味を持つ。障害に対する考え方を根底から覆すこの理論は、前述のように社会学的にもガーベン・デ・ジョングによって、自立生活運動とリハビリテーション理念の対比による当事者エンパワメントの有効性の研究に展開され、広く社会に知られることとなった。それは1980年代のWHOのリハビリテーションの考え方にも大きな影響を与えていく。その結果、WHOのリハビリテーションの定義の中に「リハビリテーションとは期間と目的を限定して行うもの」との規定が盛り込まれることとなった。
自立生活センターは重度障害者が地域で暮らすための理念的なバックボーンを提供し、また実質的に地域で暮らせるようなサービスと運動の複合組織として、当事者自身による運営組織のモデルを障害者に伝えている。自立生活センターの目的とするところは「どんな重度の障害を持っていても、地域の中で普通の人と同じような生活が享受できる社会を作り上げること」にある。
第4節 自立生活センターのサービス
自立生活センターは重度障害者が地域で各種の支援を受けて暮らしていけるようにするため、精神的なサポートとして「ピア・カウンセリング」、自立生活を継続していくための生活技能を伝えていく「自立生活プログラム」、地域での日常生活の実質的支援を行う、当事者が運営管理する介助サービス、移動のための自由を確保する車椅子用リフトサービスや交通アクセスの改善運動、街の建築上のバリアを除いたり、コミュニケーション障害者の社会参加を可能にするための各種サービスや制度の確立を要求する活動、などをするところである。
一人ひとりの障害者が地域でばらばらに暮らす中で直面した様々な困難や差別、偏見を乗り越えていくために、一人では何もできない障害者が、自立生活センターという傘のもとに集まり、組織としてその要望を行政や市民に訴え改善を図ることは、社会に障害者への差別の意識が強ければ強いほど有効に機能し、社会の意識を改善し、サービスを拡充することに寄与してきた。
ピア・カウンセリング
ピア・カウンセリングは障害を持つカウンセラーが同じ障害を持つクライエントに行うカウンセリングである。しかし一般のカウンセリングと全く違うところは、ピア・カウンセラー自身は専門家ではなく、受け手のクライエントである障害者と対等な関係を持つ仲間として、話を十分聞いてあげる存在と規定されている。ときにはカウンセラーとクライエントが10分ずつ時間を交代しあい、自らの抱える問題をお互いに聞いてもらいあう、まさに対等な関係をとる場合もある。ピア・カウンセリングではクライエントと呼ぶことはなく、ピア・カウンセリングの受講者と呼ばれたり、利用者と呼ばれている。日本の自立生活センターでは、ピア・カウンセラーになるためには、2泊3日の集中講座を受け、次に週1回で10回以上にわたる長期講座を受講し合計42時間のピア・カウンセリング講座を受けたのち、自立生活センター協議会の主催する養成講座を修了している必要がある。各自立生活センターには養成講座を受けた障害者リーダーが職員として勤務し、個人ベースのピア・カウンセリングを日常的に提供したりピア・カウンセリング講座を地域の障害者に公開して提供したりしている。
ピア・カウンセリングによって、自分の障害が自分の身体的欠損にはなく、社会の側の障害者を受け入れる態度や偏見のために普通学校や企業に就職できないことや、街の建物に階段があったり、公共バスに高い段があったり、電車の駅が橋上にあってエレベーターが設置されていないため乗れないことから障害が発生することに気付いていく。介助を受けることはこれまでは家族に迷惑のかかる罪であると認識していた障害者がピア・カウンセリングを受けると、介助は社会が提供すべき義務を持っており、障害者は介助を要求する権利があるのだということに気が付き、介助を使って自由に外出することを肯定的に受け止められるようになる。このような精神的な自立ができた障害者は家族のもとを離れ、地域の中で見知らぬ他人の介助者に介助を受けながら、自立生活センターの支援で地域生活が可能になる精神的な基盤を確立していくのである。
自立生活プログラム
ピア・カウンセリングで精神的な自己確立をした障害者は、次に自立生活プログラムを受講する。そこでは先輩の自立生活経験者たちから、地域の中で障害者として暮らしていくための日常生活上のノウハウを獲得することになる。例えば「家族との関係」の自立生活プログラムとは、家族の中で自らの主体的な自己選択・自己決定をしていく精神的な独立を目指すプログラムで、親を自立生活への規制や管理をする存在から、支援し援助してくれる存在に変えていくための当事者への支援プログラムである。ロールプレイなどを織り込んで行われる。「介助者の使い方のプログラム」は介助者を自らの活動を支援するサポーターとして活用するためのプログラムである。例えば介助者が毎回遅刻してくるようなときに、介助者を怒らせずに上手に説得する方法が先輩のロールプレイの中で示され、受講者は自分でもロールプレイをする中で実際の現場で、一人きりでも介助者と対等な関係で渡り合える存在へと成長していく。このように自立生活プログラムの中では体験を通して学んでいくという方式がとられ、知的障害を含む人たちにも有効にプログラムが機能することが確認されている。
介助サービス
介助サービスはピア・カウンセリングや自立生活プログラムの側面支援を得て、初めて有効に機能するものである。介助サービスだけ単体で提供した場合、自立生活経験の浅い障害者の場合には介助者に依存してしまい主体性を見失うことにもつながる。そこで自立生活センターでは、地域で暮らそうとする障害者にまずピア・カウンセリングと自立生活プログラムを受講してもらい、その後介助サービスを実質的に使いながら、学んだことを生かして介助者を自己管理していく方法を身に付けていく。介助者は本人の意向に沿ってそのやりたいことを支援するサポーターであり、決して障害者を保護し管理する存在ではないことを自立生活センターの介助者研修の中では繰り返し教習される。
自立生活センターではトイレ、入浴、食事作り、移動・外出・旅行など利用者のニーズがあればあらゆることに対応できる準備をしている。利用者のニーズに基づいて介助を行うのが原則であり、介助時間・内容のすべてにおいて利用者のニーズが優先される。深夜・早朝の緊急体制もあり、いつでも同性介助の職員が派遣される仕組みが作られている。介助者は自立生活センターに登録され、自立生活センターに常駐する介助コーディネーターが障害者の職員と一体となって、利用者の介助ニーズだけでなく生活相談を含めた幅広い支援を行う。介助者は自立生活センターが提供する二日間にわたる介助者訓練を受け、介助におけるマナーや介助方法を学び、さらに障害者職員による介助者への研修を受けてから利用者宅に派遣されることになる。
介助サービスはボランティアによって運営されると障害者の主体性が損なわれ、介助者の提供者側としての強い立場が行使される可能性があるため、自立生活センターでは障害者側が雇用者の立場に立ち雇用と解雇の権利を持ち、介助を受ける中で対等な関係を確立しようとしている。途上国においては介助サービス制度が確立していないことがほとんどである中で、どのように運営していくかという疑問を持たれるであろうが、自立生活センターでは行政に介助サービスを制度として実施させるために運動体を形成し、行政を変えてきた実績を国内外で有している。
自立生活センターでは介助サービスのない地域では、まず重度の介助が必要な障害者を一人選び、その障害者に介助者兼職員を雇う費用を補助し、モデルとしての自立生活者をその地域の中に実態として作り上げる。アジアの国においては、2から3年間の支援を前提に介助サービスのモデル実施を行う。この介助サービスモデルを行政に実施させるように自立生活センターは運動を平行して行い、マスコミの支援などを受け専門家や行政の一部職員の応援などを受けながら、制度化へ向けて様々な運動を展開する。韓国の場合にも自立生活セミナーを1999年に初めて実施してから自立生活モデルの支援を2年間続けたあと、自立生活センターの設立を2年目に達成し、2007年に介助サービスの国制度での実施を見るまで8年間である。タイにおいてもナコンパトムの自立生活センターでは、国の財団の支援により、介助サービスのモデル実施が2007年10月より始まっている。2008年現在、台湾・マレーシアでも介助サービスのモデル実施が始まっており、先進国モデルである自立生活センターは、アジアでは不可能であるという通説は崩れつつある。
第5節 自立生活センターの運動
自立生活センターは上記の三つのサービスに加えて、そのサービスを具体的に制度として支えるべき行政の考え方を、施設から地域の障害者支援へ変えていく「運動」としての取り組みも行なう。長い間施設中心のパターナリズムと医療モデルに基づいた福祉サービスを展開してきた先進国の行政にとって、これまでのシステムを根底から覆すような地域ケアへの転換は非常に抵抗があることがらである。すでに雇用されている施設職員の処遇問題を考えなければならないし、施設の建設費に依存してきた地方行政の体質を変えなければいけないこと、何より我が子の安全な将来の生活を保障する施設から、不安定な小規模資本の地域ケア組織に依存することの親の不安感を取り除くなど、いくつかの乗り越えなければならない障壁がある。
これに反して途上国においては福祉関係のインフラも整備されておらず、したがって施設で雇用されている職員数も少なく、先進国に比べて地域ケアに直接移行できる可能性は高い。
自立生活センターの運動には、個別の障害者のニーズや権利を擁護するための個人に対する権利擁護活動と、駅の交通アクセスや行政の制度を改善したり新しい制度を作ったりする組織的な権利擁護活動とがある。個人への権利擁護活動とは、例えば親が自立に反対する時に本人の依頼に基づいて、自立生活センターの職員が本人の自立の意思を尊重して、親の説得に協力することなどである。組織的権利擁護活動とは、たとえば駅に階段があって、エレベーターを設置しないと車椅子では使えない状況がある場合に、それを利用する障害者が声を一つに集めて運動をし、鉄道会社や行政を説得してエレベーター設置をさせることがこれにあたる。自立生活センターでは、介助サービス制度を行政に制度化させるときには、ロールモデルとしての重度障害者が地域に暮らすことを周辺の障害者が全員でサポートする。そして個人の障害者の介助ニーズを社会の中に顕在化させ、そこでいまボランティアが担っている介助サービスを行政に制度化させる。このようにして、個人の要求が全体の障害者の生活改善を導く。これは、個人の権利擁護活動が組織的な権利擁護活動に引き継がれている事例といえる。自立生活センターでは「運動なきところにサービスなし」と言われている。障害者が声を上げることによって初めて地域での福祉サービスが充実してくるという歴史的な経験則に則って言われているのである。
第6節 途上国の自立生活センターに関する先行研究
途上国の障害者から自立生活運動に対して出てくる反論としては、毎日の生きるか死ぬかの戦いをしている途上国の障害者に対して、住宅もなく、年金や所得補償もなく、家族に依存して暮らさなければならない境遇に置かれている中で、介助者を付けての自立生活というのは贅沢な望みである、とか、現実的ではない、といったものであろう。実際こうした批判はよく聞かれる。DPI元議長であるジンバブエのジョシュア・マリンガは、「われわれ(途上国の障害者」は生きるか死ぬかの戦いをしているのであって、 自立生活というような贅沢なことをいっている余裕はない」とDPIの会議で発言している。
ここでは自立生活イコール介助サービス、親元から離れての独立生活というイメージが出来上がっているようである。また政府の財政が破綻しているジンバブエの状況では、福祉制度の充実などありえないというあきらめも感じられる。
一方、中西(2008)は、途上国で自立生活運動を可能にする条件とその戦略について、ヒューマンケア協会[1]によるアジアの途上国支援全般の経験から述べている。タイについては、JICAの開発福祉支援事業として2001年より3年間行われた「障害者の自立生活研修計画」でチョンブリ、ノンタブリ、ナコンパトム3県の代表を呼んで行われたパイロットプロジェクトの内容について触れている。しかし自立生活センターと社会変革の問題については、この3年間の研修の最後で社会開発・人間の安全保障省へ、自立生活センターへの支援と重度障害者への介護派遣を政策提言したことが触れられているのみである。タイの自立生活センターの活動内容についての詳しい記述はない。
川田(2007、pp. 12-13)は、APCD[2]の活動の中で特に、ナコンパトムの自立生活センターにおける重度障害者のエンパワーメントプロセスを、野中郁次郎の「暗黙知」の概念を使って、ピア・カウンセリングの効用を説明している。川田によると、ピア・カウンセリングとは、重度障害者が人生において味わってきた深い痛みや苦しみは、非障害者には計り知れない高貴な体験(暗黙知)であり、この体験を相互に共有する場だと位置づけられている。そしてこの体験を通じて、お互いに生きようとする思いが、いまだ絶望の淵にいる他の障害者のみならず、家族、コミュニティなどの様々な人々にとってより良い社会の創出に向け変革を実践していくことになる。しかしここではピア・カウンセリングが障害者同士の連携を作り上げていくことは述べられているが、家族やコミュニティを変革していくプロセスについては説明がされていない。また川田は、重度障害者の痛みと苦しみが高質な暗黙知を生み出し、それが社会変革へのエネルギーになる、と解釈しているが、川田は障害は社会の障害者に対する差別や偏見や建築上の不備などによって起こっているものであり、それを改善することによって障害者の持つ痛みや苦しみが解消していくという視点を持たない。川田論文では社会側の問題に触れず、個人の暗黙知の共有によって社会変革がなされるとしている点に限界がある。また、川田論文ではピア・カウンセリングだけが取り上げられ、あたかもそれのみで社会変革は起こるという捉え方がされているが、自立生活センターの運動と事業体の側面のうち事業体の側面の中のピア・カウンセリング部分のみで自立生活センターの全てを語ることには無理がある。
川田論文とは異なり、久野・中西(2004)『リハビリテーション国際協力入門』の中で、久野は自立生活運動を権利概念を基礎にした権利・アドボカシー指向アプローチとして、位置づけている。自立生活センターは個人のニーズではなく障害者集団全体の社会における平等と公正を指向し、その権利を保障する行政の制度そのものを変革すると述べている。さらに久野は、自立生活センターでは行政に対して単なる要求運動をするだけでなく、まず自らがサービスを作り出し、その提供の仕組みや制度的保障を行政に求めていく取り組みを行うと、自立生活運動が「複合型アプローチ」をとると指摘している(p.
195)。
しかし久野論文では、自立生活センターでは各種のサービスを作り出しどのようにして行政を動かしていくのか、そのプロセスについては述べられていない。そこで筆者は自立生活センターを自立生活センターたらしめる指標を確定し、これを基に自立生活センターの活動が社会変革へどのようにつながっていくのかを分析することにした。
第7節 自立生活センター成立の5指標
日本の全国自立生活センター協議会では、新規の自立生活センターが協議会に加盟する条件として以下の4要件を達成することを原則としている。このうち最初と最後の項は必須要件であり、真ん中の3つのサービスのうちの2つを行う事が義務付けられている。
運営委員会の過半数と代表・事務局長が障害者であること
ピア・カウンセリング、自立生活プログラムをおこなっていること
介助サービスを行っていること
障害種別を超えてサービスを行っていること。
この4つの規約要件がなぜ自立生活センターを成り立たせるための重要な指標となっているかを、以下で分析する。
運営委員会の過半数と代表・事務局長が障害者であること
その団体が一般の団体と区別するときにもっとも重要な指標として第一にあげられるのがこの「当事者性」である。自立生活センターは障害者によって(by)運営され、障害者のために(for)活動する、障害者自身の(of)団体である。
運営委員の過半数が障害者である理由は、これまで「福祉」が資本主義社会の機能を保持するための貧困者の反乱を防ぐための安全装置として考えられてきたため、「慈善的福祉」「施しの福祉」が基調となっており、当事者のニーズは無視され、家族や専門家の意向に沿って施設が作られて障害者を隔離・虐待してきた歴史がある。
重度障害者が医療の桎梏から解放され、完全な社会参加と一般市民との平等のもとに暮らせるようにするためには、障害当事者が運営委員の過半数を占める当事者自身の意思決定によって、サービス事業体である自立生活センターは運営されなければならない。そのためにこの第一要素は自立生活センターの歴史を踏まえて開発してきた根幹となる指標といえる。
代表・事務局長が障害者であることが第一の要素の中に含まれている理由は、介助サービスなどの現場でサービス利用当事者の声が十分に反映されるためには、合理的・能率的な運営をする幹部ばかりがいても心のこもった安心のできる介助サービスは提供されないからである。
代表・事務局長はまさに日々の現場で最終決定を担う人たちであり、その人たち自身が同じ介助サービスを使う当事者であれば、自分に心地のよい、安全なサービスを求めるに違いない。自立生活センターのサービスの質が高いといわれるゆえんはここにある。自立生活センターでは、たとえ利益にならなくても、重度の障害者や、知的障害者、精神障害者の介助サービスを進んで受託するだけでなく、早朝や夜間の緊急介助の依頼にも快く応じる体質を備えている。それは、現場の最終決定を担う人たちがサービスの受益者本人であることから来ている。このことからも「当事者性」は自立生活センターを成功させるためには不可欠な指標といえる。
ピア・カウンセリング、自立生活プログラムをおこなっていること
多くの障害者はこれまで、特にアジアの諸国においては、大家族制のもとで家族のメンバーに介助をしてもらうことが多く、成人してからも親の管理や保護のもとに暮らす例が多かった。家族に囲まれた生活は一見快適なように見えるが、その実本当に自分がやりたいことや実現したいことについては家族の目を気にしながらおずおずと希望を述べ、その実現は家族の都合任せになることが多かった。障害者が自分の夢や希望を実現するために必要な支援をいつでも十分に求められるような場や機会は提供されてこなかった。
家族の迷惑や苦労を考えると、家族のもとにいて遠慮がちな生活を送るよりは、いっそ家族から離れて、遠く離れた施設で家族に束縛されない自由な生活をしようと望む障害者も出てくる。この彼らの望んだはずの自由な生活の場は、実は施設には存在していない。施設では、保護という名目の管理と、生活の規律という意味での規則や権利の剥奪が、頻繁に起こる。時には虐待や死亡事件すら報じられているのが施設の実態に近いかもしれない。施設を一度経験して地域に出て暮らした障害者は、その地域での生活がいかに苦しくとも二度と施設に戻ろうとはしないことを見ても、このことは明らかである。
重度障害者にとっては家族のもとも施設も安住の地ではない。彼らはそこでの生活経験から自分の夢や希望は決して人には語らなくなり、少しでも家族や職員に気に入られようと始終ほほえみを絶やさず、物腰も穏やかでいわゆる良い子の障害者を演じて虐待や暴力から避難しようとする。
このような、人を信じられない、夢や希望を持てない障害者たちの心を開くためには、同じ経験を持つ障害者がカウンセラーとなってその話を聞いてくれるピア・カウンセリングというツールが必要になる。自立生活センターでは、施設や親元から出たがっている障害者たちに在宅訪問をしたり、ピア・カウンセリングのセミナーを開催したりして、外の世界に触れ合えるチャンスを提供している。ピア・カウンセリングの中で初めて障害者は自分が味わっている孤独と絶望感は他の障害者とも共通するものであったことを知る。そして障害は自分の持つ身体的欠損から起こるのではなく、社会の中での障害者に対する差別の心や障害者にとってアクセス化されていない建物や公共交通機関にあることを、ピア・カウンセリングの中で気付いていく。ピア・カウンセリングは障害者が自分の障害の原因は社会に起因することを「意識化」するプロセスである(第7章第2節、p.48参照)。
そこでは現状の社会の福祉サービスや公共交通機関のバリアをともに力を合わせて取り除き、障害者の暮らしやすい社会に変えていこうという意識が生まれてくる。このような障害者が大勢集まっているのが自立生活センターであり、ピア・カウンセリングを通じて運動体としての自立生活センターはさらに強化されていくことになる。ピア・カウンセリングは自立生活センターが成立するために不可欠な指標である。
自立生活プログラムは、施設や親元にいる自分の不自由さの源泉は自立していない自分にも問題があったことに気づく過程といえる。自立生活プログラムでは、自分をよく知りぬいた家族や施設職員でない一般の市民が介助に入った場合に、その人にどのように指示を出して介助をやってもらうか、どのように伝えれば上手く自分の意思が伝わるのか、お互いに誤解が生まれたときにどのように話し合いでそれを解決していくのか、障害者として地域で暮らしていくために必要な食事作り、買い物、後片付け、電車に乗ること、切符を買うことなど、あらゆる生活の場面を想定してそれを実体験してもらう。それは体験学習コースといえる。自立生活センターでは定期的に自立生活プログラムへの参加者を呼びかけ、週一回、計10回のコースとか、施設からの自立のための集中個人プログラムなどを提供している。
障害者の学校教育の場でも、親元や施設のなかと同様に、このような体験をする場は用意されていない。一人ひとりの障害者が同じような苦労をして自立を達成するよりも、これまで障害者が経験してきた自立へのノウハウを次の世代に伝えていく障害文化の伝達を行っているのが自立生活プログラムといってよい。自立生活プログラムは自立生活センターが存続するために必要となるツールである。
介助サービスを行っていること
重度障害者にとって介助サービスがあるかないかは生命の維持にとって不可欠なことである。生命維持を図るためには家族や施設職員の介助というのもありうるが、それでは単に寝起きして食事をし、トイレをし、時おり入浴をして衣服を着替えて一日が終わるという、単に生かされているだけの生活保障でしかない。人生を同じ世代の人たちと同じように生きるためには、学校へ通い、レクリエーションに出かけ、スポーツをしたり、山や海に行ったり、就職をして働き、結婚をして子供を育て、家族とともに暖かい家庭を築くなど、あらゆる場面での介助が必要となる。社会には障害者が同世代の人と同じ生活を享受できるようにする義務と責任があり、2006年12月に国連で採択された障害者権利条約の第19条の自立生活の条項では「すべての障害者は地域で介助などの支援をうけ、暮らすことができる」と記されている。
しかし国が施設やグループホームなど隔離収容の場しか用意してこなかったため、地域で暮らすという選択肢が実質的には許されていないことが多い。そこで各国の自立生活センターが取り組んでいるのが国による介助サービスの制度化である。そのためには自分たち自身でモデルとなる介助サービスを行い、その実施モデルを行政に示していくことによって、行政のなかに公的介助サービスの必要性の認識をもたらす必要がある。
介助サービスがボランティアベースでも一時的に行うことはできるが、定期的な朝晩の寝起こし介助や、トイレ・入浴などの生活で必須の介助は有償ベースで行わなければ、非常に不安定な生活になってしまう。
そこで自立生活センターが存在し、介助ニーズのある重度障害者が利用者としており、介助サービスを使っている現場を作って行政に見せていくことがいま必要である。「ニーズ無きところにサービス無し」といわれるように、ニーズが顕在化していないのに行政にサービスを請求したところでそのサービス拡大は実現しない。
どこの国の介助サービスも、障害者が地域で暮らすという実態があってその後を追って行政のサービスが生まれている。公的な介助サービスがなければ、ほとんどの障害者が自立生活を継続することはできない。自立生活センターにとって公的介助サービスは不可欠であり、それを生み出せるかどうかは自立生活センターが介助サービスを維持・継続できるかどうかに関わってくる重要な指標である。
障害種別を超えてサービスを行っていること
これまで身体障害者を例にして自立生活センターの内容について少し詳しく説明してきたが、日本の自立生活センターの規約として障害種別を超えてのサービスを求めている理由は、社会はこれまで障害者を差別して取り扱ってきたが、障害者自身が他の障害を持つものを差別してはいけないという意味で自立生活センターではこの規約を設けた。また運動体としての自立生活センターにとっては行政交渉の立場としては、障害種別を越えた要望と位置づけたい。行政の目から見ると障害は一つの塊であり、その中に身体、知的、精神が含まれているからである。一部身体障害者の要求のもとに制度を作ることはできないという行政の立場は理解できる。そのためにもこの規約は重要である。
そこで他の障害者とどのような点で重なる部分があるかを考えてみると、衣食住は3障害共通であるほか、移動については視覚障害者にはガイドヘルパーが必要であり、知的障害者は駅の表示や電車の乗換えなど移動外出の支援は明らかに必要である。聴覚障害者には移動は一見自由に見えるが、音声でのメッセージが伝わらないので駅や行政の窓口や街を歩いているときなど、支援が必要になる場合がある。
3障害とも所得の保障がなければ衣食住もままならない。生活のほぼほとんどの領域で障害種別を超えて同じようなニーズがあるかぎり、すべての障害者は団結し運動や要求活動を続けていくことが、お互いのメリットになる。
運動体としての自立生活センターは、外に向かって強くなるためにも、内に向かって互いの障害者のニーズを理解しあうことによって共通の目標に到達する連帯感が醸成される。そして組織として強化されていくメリットがある。自立生活センターが障害種別を超えてサービスをおこなったり、共同で活動することは、自立生活センターが成立するために欠かせない1指標となっている。
以上が日本の自立生活センター協議会の自立生活センターの4要件であるが、自立生活センターの理念を履行するために重度障害者の参加とサービス利用は欠くことのできない基準であることが認識されてきたために、次の要件がさらにつけ加わった。
重度障害者がサービス利用者になり、運営に参加すること
この第5の要件は、日本の全国自立生活センター協議会が2000年から2003年にかけて、国の介護保険制度への障害者介助サービス制度統合の動きを阻止する運動を起こした際に設けられた。当時全国に自立生活センターの無い県が17あったため、これらの県にも全て自立生活センターを設立し、全国配備の体制をもって厚生労働省の動きを牽制しようとしたのである。そこで「全国自立生活推進協議会」を急遽設立し、その時に決められた規約がこの新要件である。「全国自立生活推進協議会」では、自立生活センター協議会のなかで巨大な介助サービス事業を行っている団体から寄付を募り、新規の自立生活センター設立のための介助者兼職員の給与と事務所運営経費の無利子貸付制度を行った。この制度によって3ヶ年で70ヶ所の自立生活センターが立ち上がり、無配置県が一掃された。
当時介助サービスを運営すれば金になると考える障害者や団体が増える可能性があり、それを阻止するためにも、「全国自立生活推進協議会」では、最大の生活支援ニーズを持つ重度障害者が介助サービスの利用者になり、運営に参加することを義務付けたものである。このことによって「全国自立生活センター協議会」のもつ4項目の入会要件をこえる要件を「全国自立生活推進協議会」は持つ事になる。その結果、新規に「全国自立生活センター協議会」に加入してくる団体は全て、介助が必要な重度障害者が運営の中核を握っており、しかも利用者の中に1日24時間に近い介助が必要な重度障害者が最初から組み込まれた自立生活センターしか新規には生まれないシステムができあがった。このシステムは非常に強固で、全国で広域に重度障害者が自立生活する実態を作り上げ、厚生労働省も全国的な制度の中に重度障害者の介助サービス制度を読み込んだものを作らざるをえないようになってきている。
自立生活センターは、重度の障害者が利用者であれば、そのニーズに合わせて当事者のために全員で要求運動を行うので、行政もその人に必要なだけのサービスを最終的に提供するようになる。軽度の障害者のみが利用者であれば、必要以上の長時間の介助サービスは提供される可能性はない。
重度障害者は家族や施設の中で、夢や希望を訴えても実現の可能性はなく、周囲に迷惑をかけるからと、遠慮をし続けてきた。そこでピア・カウンセリングや自立生活プログラムは初めて自分の本音を語れる場として、当事者がエンパワメントしていく上で不可欠な機会を与えた。
ピア・カウンセリングで、自己尊厳を取り戻し、障害は社会が障害者に配慮してこなかったために起こっていることで、自分の身体的欠損のゆえに起こっているのではないことに気付いた重度障害者は、自分の障害が重いから人に迷惑をかけ、何一つ自分では出来ないと悩むことなく、障害は社会の責任でカバーされるべきである、そのサービスや支援を受けて生きて行っていい存在であると気付いていく。
自立生活プログラムでは、重度障害者に社会の中で生きていくために必要となる知恵や経験を先輩の障害者が後輩の障害者に伝えていく。公共交通機関のアクセス化も電動車いすに乗る重度障害者が、町に住んでいなければ起こらない。自立生活センターの5つ目の指標は自立生活センターが自立生活センターであるために必要な指標なのである。
第8節 障害当事者と社会変革をめぐる先行研究-フレイレによる対話型エンパワメント論と自立生活センター
フレイレ(1979)は、ファシリテーターが一方的に必要な知識や教育を当事者に施す「銀行型アプローチ」を批判し、ファシリテーターは対話を通じて変化を引き起こす触媒であり、当事者は知恵と考える能力を持つ主体になりうるとの考え方を持って「課題提起型アプローチ」を提唱した。銀行型アプローチとは、開発の指導者がすべての知識を持ちそれを伝達する十分な能力を備えていると考えており、一方対象となる人々は無知で何の考えもなく生きている空の存在であると前提している。このようなアプローチでは当事者のエンパワメントはいつまでも図れず、指導者に寄り掛かりその指導や指示を待って動くような人しか生まれてこない。「開発プロジェクト」は常に期間があって指導者は撤退していくので、指導者が居るうちは幾分かの成果をあげられるが、指導者が帰国したり、変わったり、プロジェクトが終了してしまえば、人々の考え方は旧態依然として、自分たちの問題は自分たちの知識や能力がなく解決できないのだ、という思い込みが続くことになる。指導者がいなくなっても社会を変えていくことによって、自分たちの生活が改善し向上していくのだという視点をいつまでも持てないことになる。
課題提起型アプローチはこれと対照的に、人々がもともと自分で考える能力を備え、すでに自分の経験からその地域に合わせた必要な知識を備えていると考える。人々の能力を信じその能力を伸ばしていくファシリテーターの役割を果たすのが開発の担当者に必要な支援だと考えられている。ここではファシリテーターも完璧な存在ではなく人々と交流し対話する中で彼ら自身がまた学び成長していく存在だと捉えられている。ファシリテーターと地域住民がお互いに会話する中で、いまある現実を客観的に見つめなおし、それを分析し、新たな見方を発見し、新たな行動を一緒に組み立てていく、そのようなプロセスが想定されている。
障害者の運動の中でも「銀行型アプローチ」に対置するのが「リハビリテーションの理念」であり、その中では障害者は意思決定能力のない病人や患者とみられ、リハビリテーションの専門家が指導し教育する歴史が1970年代まで続いた。これを現在では医療的アプローチと呼んで、WHOの障害程度区分の中でも批判を受け、新しいアプローチである障害の社会モデルが提唱されるようになった。
フレイレの『伝達か対話か』(1982)の中では、ファシリテーターと対話することによって、人々が持つ知や考え方を正しくないものとして本人自身が気づき、改めていく「対話型アプローチ」がとられるが、自立生活センターでは同様に「ピア・カウンセリング」の手法がとられる。この中では障害を持つピア・カウンセラーが対等な関係で本人の自立の過程に寄り添い、本人が気づかなかった障害の持つ意味を社会の抑圧や差別がそれをもたらしていることに気づかせることによって、本人の自立への意欲を高めていく。施設や親元で夢や希望を一切表明することができなかった障害者が、自立生活センターに来て初めて自分の夢や希望を語りだすのはピア・カウンセリングの中である。障害は本人の責任ではなく、街のアクセスや、障害者に必要な介助などのサービスを提供しない社会の側に問題があること、すべての市民と対等な生活を享受する権利が一人ひとりの障害者にあることに気付いていくプロセスがここにある。フレイレの場合と同様にピア・カウンセリングでもピア・カウンセリングによって障害は社会の環境によってもたされていると気づいた障害者は運動に目覚めたり、エンパワーして活力に満ち溢れる存在となり、その影響がピア・カウンセラーに伝わり、さらにお互いにエンパワメントしあう関係となる。
フレイレのアプローチでの教育者と被教育者の関係性は、自立生活センターではピア・カウンセリングという対等な関係での障害者のエンパワーメントツールとして具体化されている。フレイレはその「対話」を通して差別を「意識化」し、「社会変革」につなげていくが、自立生活センターでも障害は社会の環境がもたらすものであるという理解を障害者ができるようにピア・カウンセリングや自立生活プログラムが行われ、社会を変革していくことが目指される点で共通点がある。
本研究では、障害当事者が対等な対話を通じて自己の障害概念を定義しなおし、障害の原因を社会のありように求めて、その変革への行動を起こしていくプロセスを「エンパワメント」と定める。
第9節 仮説の設定
途上国においても重度障害者が中心になって運営する自立生活センターが成立しうること、そしてそれを基盤として、障害当事者のエンパワメントによりニーズを顕在化し、福祉サービスの向上を促し、社会変革につながることを、本研究の仮説とする。
この仮説を図2-2を使い具体的に説明する。
自立生活運動の理念によって重度障害者は、介助を受けて暮らすことは権利として社会に要求できることだと気付く。自立生活センターは、ピア・カウンセリングや自立生活プログラム(ILP)、介助サービスなどのツールを使って、障害者のエンパワメントを支援する。
重度障害者たちが自立生活センターの支援によって家族や施設の保護や管理から逃れ、地域で暮らし始めることは、地域社会に重度障害者のニーズの顕在化を引き起こすことになり、行政が福祉サービスを構想する原点となる。
一方、自立生活センターは重度障害者の声を集め、そのニーズを行政に訴え運動を展開する。地域での重度障害者の自立モデルが行政の制度の枠組みを作り、社会福祉サービスが提供されるようになる。重度障害者が介助者とともに社会に参加し、公共交通機関やバリアのある建物を改善する運動を起こすきっかけができる。重度障害者が地域社会で暮らすことは地域住民の意識を変え、また行政の意識もそれに伴ってしだいに変わってくる。社会的インフラとしての公共交通機関や建物・道路などのバリアフリー化が進展し、コミュニケーション支援などすべての社会的弱者にとって暮らしやすい社会が実現していく。
障害当事者はますます社会に参加するようになり、エンパワメントが強化される。どの重度障害者も自分のニーズを表明し、当事者主権を発揮して地域行政や社会を動かすことによって、ニーズ中心の福祉社会が実現する。
ここでいうニーズとは、重度障害者の必要とするあらゆるデマンドである。上野(2008)は、ケアに対するニーズの定義としてメアリー・デイリーの定義「依存的な存在である成人または子どもの身体的かつ情緒的なニーズを、それが担われ、遂行される規範的・経済的・社会的枠組みのもとにおいて、満たすことに関わる行為と関係。」を挙げている。しかしディリー(Daly
2001, p.36)がいうニーズとは、行政の経済的状況や社会の規範の枠組みが認めた範囲内でのニーズをさしており、重度障害者が生活の中で必要とする同世代の人々と同じレベルの生活を営む上での最低限のニーズとは異なるものが定義されている。『ニーズ中心の福祉社会』(上野・中西 2008)でいう当事者ニーズとは、客観より主観を、一般的より個別的を、制度よりは承認過程を、重視するようなものである。つまり当事者ニーズとは、個人の障害者が、自立生活をしてこれまで気づかなかった自分のニーズに気づき、それを行政に訴えて承認を求め、新たな制度化につなげて行く動態的なものである。
筆者は重度障害者のニーズが、それが現状の社会の経済的・規範的基準に合わないからといって排除するのではなく、障害当事者の意見を十分聞いてその当事者ニーズに沿った解決をすべきであるという立場をとる。
ニーズ中心の福祉社会とは、同世代の人たちと同等の生活を、障害者が享受するために必要となるサービスやその制度を社会に作らせていくことであり、その社会を実現するために障害者個人がエンパワメントし、自己選択・自己決定できるような自立した個人をめざすことが当事者主権の社会を実現することにつながる。図2‐2は個人のエンパワメントと行政のサービスの向上が相互作用として新たな福祉制度を生み出し、それがさらに自立生活センターの活動を強化し、行政や社会の意識変革を促し、さらなる障害者のエンパワメントと社会参加を促すことによってバリアフリーな社会を構築する基盤となり、ニーズ中心の福祉社会の実現と当事者主権の確立した最終ゴールへ導かれることを示している。
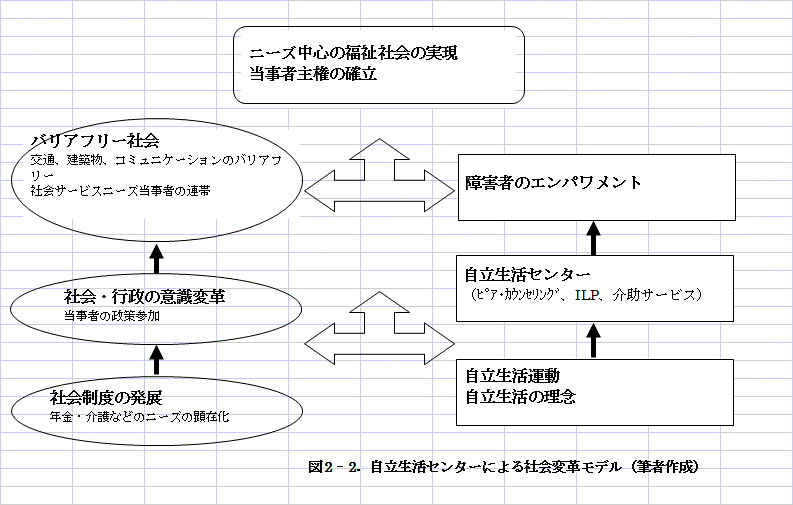
第3章 タイの自立生活センターの事例研究
第1節 タイにおける障害者のおかれた状況
タイの人口は2002年現在、63,303,000人であり、そのうちの1.7%が障害者であり、1,098,000人の障害者がいる(2002年国勢調査局)。
タイ統計局(NSO, National Statistical Office)は、タイで最初の障害者のデータとして1970年の人口住宅国勢調査を採用していた。しかし、1974年以降2001年までは保健福祉調査によるものである。
2002年については障害者調査が初めて行われている。表3-1は、その調査結果を示したものである。
表3-1 障害者数と障害者割合の変遷
|
全国総人口 |
障害者数(単位:千人) |
障害者割合 |
| 1970 年人口住宅国勢調査 |
34,397.4 |
142.2 |
0.4% |
| 1974年保健福祉調査 |
39,796.9 |
209.0 |
0.5% |
| 1976年保健福祉調査 |
42,066.9 |
245.0 |
0.6% |
| 1977年保健福祉調査 |
44,211.5 |
296.2 |
0.7% |
| 1978年保健福祉調査 |
45,344.2 |
324.6 |
0.7% |
| 1981年保健福祉調査 |
47,621.4 |
367.5 |
0.8% |
| 1986年保健福祉調査 |
51,960.0 |
385.6 |
0.7% |
| 1991年保健福祉調査 |
57,046.5 |
1,057.0 |
1.8% |
| 1996年保健福祉調査 |
59,902.8 |
1,024.0 |
1.7% |
| 2001年保健福祉調査 |
62,871.0 |
1,100.8 |
1.8% |
| 2002年障害調査 |
63,3030.0 |
1,008.0 |
1.7% |
Source:1. Survey on health and welfare 1974 to 2001 by
National Statistical Office
2. Survey on disabilities and impairment 2002 by National Statistical
Office
出典:The 3rd National Plan on Quality of Life Development of Persons
Disabilities 2007-2011
表3-1によると、1986年から1991年の間に障害者割合の増加が見られる。それは、1991年に障害者リハビリテーション法が制定され、障害者登録制度[3]が始まったためである。
表3-2 障害種別障害者数とその比率
| 障害種 |
合計 |
% |
| 肢体不自由 |
512,989 |
46.6% |
| 聴覚・コミュニケーション障害 |
240,904 |
21.9% |
| 知的障害・学習障害 |
222,004 |
20.2% |
| 視覚障害 |
123,157 |
11.2% |
| 精神・行動障害 |
81,262 |
7.4% |
出所:Report of Disabled Persons Survey 2001, National Statistics
Office,2001年のデータを基に作成:田中[4]前掲。
障害種別割合では、およそ半数の46.6%が肢体不自由で最も多い。さらに聴覚・コミュニケーション障害、視覚障害を合わせると、79.7%と全体の約8割を身体障害が占めることになる。
筆者がDPI[5]の元地域開発官トッポン・クンカンチットに聞いたところによると、タイの障害者団体は、政府から宝くじの販売権を任されている。街頭には多くの障害者が露店を出している。障害者から宝くじを買うと「良い行い」(タンブン)をしたことになるのでよく売れている。タイは上座部仏教国であり、障害は前世に罪を犯した人が現世でつぐないのために負わされていると見られている。障害者を見る人の目は、罪を犯した人たちに対する憐れみの感情はあっても、障害者を対等な人間として扱おうとはしない。庶民は現世で罪を犯したことを来世で咎められないように、貧しい人や障害者への寄進(タンブン)として金品を贈ることを習慣としているという。石井(1995,116p)は「「タンブン」の宗教とは・・・みずからの運命をみずからが支配する可能性を教える希望の宗教である。苦しみから解脱するという消極的なものでなく、「ブン」を築きあげ、積極的に幸福をつくりだす道を教える宗教なのである」と述べている。
トッポンによると、タイの重度障害者は、これまで大家族制の中で家族が面倒を看ることで、その存在も地域の人に知らされないまま、医療的ケアもなく福祉的なサービスを受けることもなく放置されてきた。椰子の実を取るために木に登り転落して脊椎損傷になるものが多かったが、近年はスポーツや交通事故により障害になる人も多くなっている。ポリオや脳性まひの障害者もおり、知的障害者は施設に収容されてもいるが大多数は放置されているという。2008年4月JICAの「マレーシア障害者福祉プログラム強化のための能力向上計画」に参加したタイ知的障害者協議会の会長は、タイの施設において現在も初潮を前にした児童の子宮摘出がなされていると報告している。タイの障害者に対す人権侵害が起こっている現実がある。
自立生活センターが求められる理由は、医療の発達で障害者が生きられるようになったこと、経済的に豊かになり、障害者の生活支援についても国や地方行政が目を向けるようになってきたことによる。
ナコンパトムで筆者が会った重度の障害者の中には、障害を負ったことで離婚され息子の嫁に看られているが、家族が介助に疲れて放置され、異臭を発するマットの上に寝かされている人もいた。この環境の中では泌尿器の感染や床ずれなどを起こす可能性が非常に高く、援助もないまま死を待っている状況の人もいた。
国の政策として障害者福祉が扱われるのは、1979年に諮問機関として作られた「障害者のリハビリテーションと福祉に関する四つの小委員会」の一つである「障害者の援助のための行政および立法に関する小委員会」が、障害者リハビリテーション法を起草したことに始まる。同法案は1991年、障害者に関する最初の法令として立法化された。しかしこのとき、タイ障害者協議会(Council
of Disabled People of Thailand)を中心に、同法案では公共施設のアクセスや雇用への援助策が不十分であるとして、反対運動が起こっていた。この中心となったのがDPI(障害者インターナショナル)
タイ議長のナロン・タキバタラキッチであり、彼の周りに後のDPIアジア太平洋の地域開発官(RDO)のトッポンや後のナコンパトム自立生活センターの所長となるティラワットがいた。
ティラワットは、この時の運動が障害者の実際の生活には何の変化ももたらさなかったことが、自立生活センター設立への動機だと述べている。
第2節 ナコンパトム県の概況
ナコンパトム県はバンコクの西方56キロにあり、タイに始めて仏教が伝わった場所といわれている。現在も自立生活センターの近くには紀元前3世紀にインドのアショカ王が建てたといわれる美しい仏塔があり、観光客が訪れる。
ナコンパトム県の人口は815,122人(2000年)、面積は2,168.3平方キロメートルでほぼ東京都の面積に匹敵する。ナコンパトム県の中は7つの郡(アンパー)とナコンパトム町に分かれており、その下に105の村(タンボン)、919の区(ムーバーン)がある。
現在自立生活センターは国道4号線沿いに2カ所あり、周辺のタンボンへもサービスを提供している。
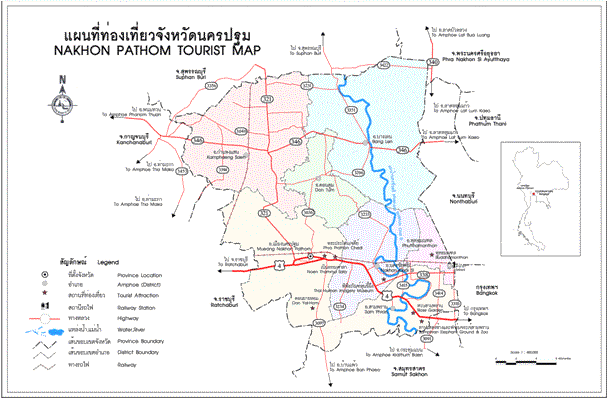
図3-1 ナコンパトム県全図
(出典 http://www.tourismmart.com/storefront/province_desc.asp?pvid=273&countryid=1)
〈タイの県行政組織図〉
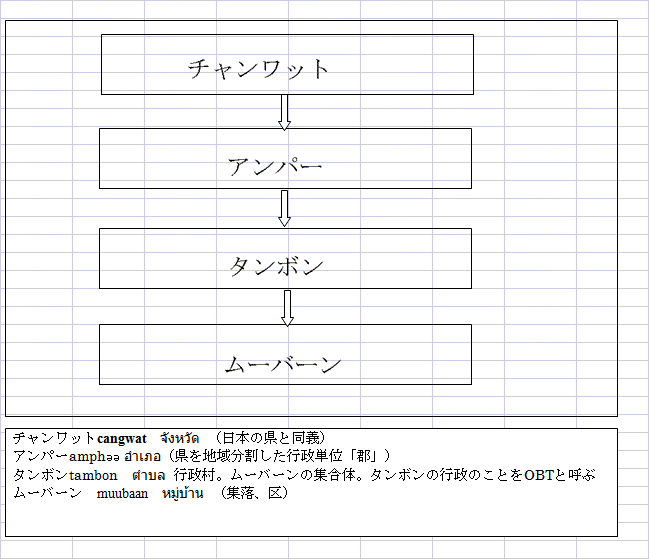
図3-2 県行政の概念図 (筆者作成)
第3節 調査対象
タイには2008年7月現在7箇所の自立生活センターがある。APCDの研修が始まったころから運営されているのは、バンコク市の近郊にあるノンタブリ県の「ノンタブリ自立生活センター」、観光地であるチョンブリ県のパタヤにあり、レデンプトリスト職業訓練学校と併設されている「チョンブリ自立生活センター」と「ナコンパトム自立生活センター」の3つである。これらに加え、バンコク自立生活センター、パトンタニ自立生活センター、プッタモントン自立生活センター、そしてチョンブリ県の南東にまだグループとして始まったばかりの団体が活動中である。
これらの自立生活センターの中で、ナコンパトム県の自立生活センターを調査対象として選んだ。その理由を以下に説明する。
ナコンパトム自立生活センターは、タイの自立生活センターの中でもっともすぐれた自立生活センターといわれる。その理由は、第1に自立生活センターの基本的なサービスであるピア・カウンセリング活動が、日常業務の中で毎月頻繁に行われていること。第2に視覚障害者を含め障害種別を越えた活動が目指されていること。第3に完全に独立した自立生活センターとしてスタートしており、そのため財政的にも非常に苦しい状態でありながらそれを克服してきた点である。したがって、成功要因を分析するには好例である。調査対象であるナコンパトム自立生活センターの詳しい説明については、第4章の第1節で行う。
ノンタブリの自立生活センターは、DPIのRDO(地域開発官)であったトッポン・クンカンチット(2007年死去)の存命中は、ノンタブリのDPIオフィスに併設されており、財政的にも運営の面でもDPIアジア太平洋オフィスに負うところが多かった。そこで調査対象として考えた場合、運営組織の分離ができていなかった期間が長く、独立した自立生活センターとしての調査はできないため、調査対象からはずした。ただしノンタブリ自立生活センターは、DPIからの分離後は活発な活動を展開しており、学校や市の建物のアクセス運動やタンボンからの支援を得ての自立生活プログラムの実施などの面ではよく活動しているといえる。トッポンが幹部軍人養成大学卒業生であったのと同様に、現代表のティラユットは幹部警察官大学の卒業生で、高級官僚の同窓生が多い。さらに彼は政府の介助制度研究委員会の委員を務めるなど、中央に近い政治力を持った自立生活センターといえる。ティラユットは頚髄損傷の四肢麻痺者で介助が必要であるが、トッポンと同様に妻がおり、介助の必要度は低い。その一方でピア・カウンセリングについては1人しかリーダーがおらず、当事者個人のエンパワメントが十分でなく、いまだ軽度の身体障害者のみが対象とされてということでは不十分な点がある。
次に、チョンブリの自立生活センターは、障害者主導で運営されている「レデンプトリスト職業訓練学校」で働く障害を持つ教師たちが中心になって運営している。パタヤ障害者協会という地域障害者団体との連携を持っているものの、運営の中核は教師陣が握り、センター代表のウドムチョクも現役の教師である。彼も頚髄損傷の四肢麻痺者であるが、比較的軽度で身の回りの事は全てできるという意味では、日常生活への介助が必須と言うわけではない。そのことが介助サービス制度を国に作らせていこうという迫力に乏しいように見えるのかもしれない。また、パタヤの自立生活センターが、レデンプトリストが職業訓練校から財政的・人員的支援を得ているために、調査対象としては選ばなかった。しかしパタヤ市やチョンブリ県との関係は良く、自立生活センターの自立生活体験室を含む建物が市の援助で作られているほか、観光都市であるパタヤ市内は、彼らの運動の成果でほとんどの建物や道路がアクセス化されている。これを見ると、タイの自立生活センターの中で地域活動を重視した自立生活センターとして特殊な地位を占めている。自立生活体験室では、病院からの退院後に行き場を失った障害者を受け入れて介助を提供している。この点では、自立生活運動の理念に忠実に運営されているが、ピア・カウンセリングがほとんど実施されていない点では日常活動の弱さを感じる。全国の障害者を対象とした自立生活運動に十分に取り組めていないことは、重度障害者を対象とした自立生活センターが実現していないから生活を守る制度確立活動が多少弱いといえるかもしれない。新規にできた4団体のうちプッタモントン自立生活センターは、ナコンパトム自立生活センターから派生してできた団体で、運営や職員の交流の面でも密接に活動している。そこでナコンパトムの自立生活センターの調査においては、同一団体の別部門のような扱いで調査対象に含めた。
2007年以降にできたその他の新規の自立生活センターについては、まだ活動内容も確定しておらず、自立生活センターの職員訓練を経ていない人たちが中心になって運営している。自立生活センターの理念が十分浸透しているかどうか定かではない。そのため調査対象からはずした。
第4節 調査方法
調査日程
2007年12月17日~26日まで現地調査を行ってきた。予定より入国日を1日早め、帰国日を1日伸ばした。よって実質的な調査日は、12月17日~26日の10日間となった。結果として10日間あったことで、支障なく調査ができた。
表3-3 ナコムパトム調査全日程 2007年12月17日(月)~26日(水)
| 12月17日(月) |
通訳者との打ち合わせ。
現地ナコンパトム自立生活センター所長との日程確認
ナコンパトム県内ホテル宿泊。
事務所全体の運営について
所長ティラワット聞き取り①
事務局長ナンタ聞き取り①
利用者親クンラチャート聞き取り①
事務所全体の運営について |
ナコンパトム県内ホテル宿泊
ナコムパトム自立生活センター |
| 12月18日(火) |
thungbua タンボン、
タンボン長:Wiira Laurujiraalay さん聞き取り
ピアサポートグループの最終日に参加 |
ナコンパトム県
ガムベーンセーン・アンパー |
12月19日(水)
夕刻 |
プッタモントン自立生活センター訪問
所長、事務局長面接調査。
車中ピア・カウンセラーであるトンチャンからピアカウンセラーになる条件について聞く
ターダムナック・タンボン長訪問
近所の住人からの聞き取り
|
プッタモントン
ターダムナック・タンボン
ナコンパトム |
| 12月20日(木) |
タイの新リハビリテーション法といわれる
「障害者の生活の質の開発に関する国家計画」についてのセミナーに参加 |
バンコク市
於 タイ「社会開発と人間の安全保障省」
タイ自立生活センター協議会主催 |
| 12月21日(金) |
OBT(タンボン村役場)でのピア・サポートグループ
午後休息、資料整理 |
ターダムナック・タンボン |
| 12月22日(土) |
ピア・カウンセリングと自立生活プログラム利用者、介助サービス利用者への面接調査。(3名の自宅を訪問)
利用者家族と地域住民への面接調査。 |
ナコンパトム |
| 12月23日(日) |
休日のため、午前中調査の資料整理。
夕刻所長ティラワットの自宅訪問追加聞き取り |
ナコンパトム |
| 12月24日(月) |
ボーントーイ・タンボンを訪問し、村長からの聞き取り後、ピアサポートグループに参加した。午後ノンタブリ自立生活センター職員と利用者の面接調査 |
ナコンパトム |
| 12月25日(火) |
介助者、利用者、職員、家族(在宅訪問)面接調査、事務局長の追加面接調査 |
ナコンパトム |
| 12月26日(水) |
サラヤ・タンボンを訪問し、地図など資料をもらう
午後聞き残したことの確認と資料をもらう |
ナコンパトム |
調査方法
本調査は障害者の自立という精神的・社会的な要因を含む課題を取り扱っており、従来の数量的調査では計れない内容が含まれている。そのためフィールドワークを行って、個別の障害者やその人の周辺でその生活を支える家族・行政・自立生活センターの職員などの個人的な面接調査が欠かせない。そのためここでは質的評価方法を取り入れることにし、フィールドワークによる面接調査を行った。
タイ・ナコンパトムの自立生活センターが成功していると周辺の専門家や行政、他の障害者団体の人たちは言うが、なぜそれが成功したのか、その成功にはどのような要素が関わっているのかが、ここでの課題である。第2章7節で提示したように、自立生活センター成立の指標といわれるのは、運営委員会の過半数と代表・事務局長が障害者であること、ピア・カウンセリング、自立生活プログラムをおこなっていること、介助サービスを行っていること、障害種別を超えてサービスを行っていること、重度障害者がサービス利用者として必ず対象となり運営に参加することが義務付けられている、の5つである。この指標がどのようなプロセスや関係によって達成されたか、またその結果、個人の障害者がエンパワメントし、行政や社会を変えたかどうか、ということを、フィールドでの面接調査を通じて確認していく。
面接調査の対象
自立生活センターには、運動のリーダーとして、またサービス提供者としての所長の他、事務局長、職員、介助者、ピア・カウンセラーと、サービス利用者であるピア・カウンセリングや自立生活プログラムの参加者と介助サービスの利用者が存在する。サービス提供者側は利用者からどのような反応を受け取っているか、また利用者はサービスの質や内容について満足しているか、自立につながる支援を得られエンパワメントしたかどうかを、それぞれから直接聞き取った。
しかしながらサービス利用者と提供者の調査だけでは客観的とは言えないので、第三者的な立場にいる県・市・地域行政に聞き取りを行うことで、第三者が自立生活センターをどう評価しているかを調査した。
表3-4 ナコンパトムおよびプッタモントンILセンターの職員と利用者一覧
|
氏名 |
役職・役割・その他 |
| Mr. Teerawats Snipatomsawad |
ナコムパトム自立生活センター所長、四肢麻痺 |
| Ms. Nanta Songpeenong |
ナコムパトム自立生活センター事務局長、介助サービスコーディネーター、車いす利用、脊髄損傷 |
| Mr. Santi Rungnasuan |
プッタモントン自立生活センター所長、四肢麻痺 |
| Mr. A |
ナコムパトム自立生活センター、ピア・カウンセラー職員、介助利用者、電動車いす利用、脳性マヒ |
| Ms. C |
ナコムパトム自立生活センター、ピア・カウンセラー、骨形成不全、車いす利用 |
| Mr. B |
ナコムパトム自立生活センター、会計担当職員、頚髄損傷、電動車椅子利用 |
| Mr. K |
ナコムパトム自立生活センターのピア・カウンセラー、頚髄損傷、四肢麻痺、絵を書く事で生計をたてる |
| Mr. I |
73歳の母親と同居、頚髄損傷、四肢麻痺、自宅で15年寝たきり、車いす利用 |
| Mr. P |
介助サービス利用者、四肢麻痺、頚髄損傷 |
| Mr. V |
プッタモントン自立生活センター、視覚障害者職員 |
| Ms. T |
ナコムパトム自立生活センター職員、ポリオ、歩行障害、女性、会計事業報告担当 |
| Mr. O |
車いす利用、火傷による四肢損傷、ピア・カウンセラー |
| Mr. E |
頚髄損傷、四肢麻痺、妹と同居、妹が介助 |
| Mr. W |
ナコムパトム自立生活センター、介助者兼職員 |
| Mr. R |
介助サービス利用者、姉が介助、脊髄損傷、車椅子 |
さらに利用者の家族や地域住民から、利用者が自立生活センターの支援によってエンパワメントされたかどうかの評価を聞いた。このようにサービス提供者、利用者、第三者からの聞き取り調査によって、ナコンパトムの自立生活センターが5つの指標において成功しているかどうかを、その条件とプロセスを含めて確認を試みた。
調査実施方法
京都大学博士課程の学生で在タイ3年目の吉村千恵が通訳をしてくれた。彼女はナコンパトム自立生活センターの職員とも知り合いで、相手側の緊張を解いてくれた。自立生活センターについても、日本で介助者をしていたこともあって詳しく、的確な通訳をしてもらえた。介助者としては、筆者自身の自立生活センターの職員に来てもらった。DPIのオフィスから、リフト付バンを運転手とともに借りたため、体力的にも楽に調査できた。
3名のチームで、ノンタブリの自立生活センターから10キロのところにあるホテルに泊まりこんで調査を行った。録音機、カメラ、コンピュータを持参し、メモでの記録を同時に取りながら面接調査を行った。
筆者自身がナコンパトムの職員に自立生活センターの理念、運営、サービス等を教えた当事者であるため、問いに対して好意的・肯定的な評価を述べる蓋然性が高いと思われた。そこで、あえて否定的な質問を多くした。そのせいもあって、困難や上手くいっていない分野のことについてもある程度聞けたと思っている。
主たる面接場所が事務所であり、他のメンバーも回りにいて聞いているため、必要に応じて、(例えば利用者の場合には)他のメンバーに外に出てもらって質問するなど工夫をした。また職員間の問題を聞く場合には、移動中の車の中などでバイアスのかからないような状況をできるだけ作って、ピア・カウンセラーの仕事に就いた動機などを聞くことができた。
毎晩資料の見直しをしたほか、記録した資料や写真の整理を中日に行った。また質問表と聞き取り記録を対比し、聞き漏れがないように務めた。
第4章 ナコンパトム自立生活センターの設立と展開
第1節 ナコンパトム自立生活センターの設立過程
ナコンパトム県のナコンパトム町に、ナコンパトム自立生活センターは存在している。センターの発足は2002年のAPCDによるセミナー開催後にさかのぼることができる。APCDのセミナーには現在所長のティラワット、事務局長のナンタ、プッタモントン自立生活センターの所長でありピア・カウンセラーであるサンティの3名が参加していた。タ イの中心のバンコクからは40キロも離れているため、ナコンパトムセンターを訪れる人も少なかったのと、職員すべてがタイ語しか話せず、英語でのコミュニケーションができなかったこともあって、その実態が知られるようになってきたのは2004年のAPCDの正式な開所後APCDのセミナー参加者が訪問するようになってからである。
現在の職員数は、ティラワットとナンタ以外に障害者職員が6人と常勤の運転手兼介助の男性1名、事務担当の女性職員1名の計10名である。事務所は商店街の中に立地しており、重度障害を持つ人たちは電動車いすで通勤可能な範囲内に住んでいる。事務所にはコンピュータが5、6台設置されており、奥に炊事室と自立生活体験室が設置されている。絵画が20枚ほど壁いっぱいにかけられている。これは重度障害者が口で描いたもので、自立生活センターの運営資金の一部になるとともに本人自身の収入にもなっている。
ナコンパトム自立生活センターの所長であるティラワットは、2002年から2004年にかけてJICAがヒューマンケア協会と共同して行った「タイ障害者の自立生活研修プログラム」の第一期からの参加者である。彼は学生時代に四肢麻痺になり、電動車いすに乗っている。日常生活のすべてに介助が必要な重度障害者である。1983年のDPIアジア太平洋評議員会がタイで開催されたときに、その事務局を手伝っており、その頃からナコンパトムに障害者団体を作る活動を始めている。
ナコンパトムにティラワットが作った障害者団体は、2004年にピア・カウンセリングと、障害者の自己決定の実現やアクセスの改善を求めるアドボカシーの活動を開始した。その活動の中で利用者から、ピア・サポートグループの結成と、介助者派遣サービスの必要性が訴えられた。2006年前後よりアドボカシー活動、ピア・カウンセリングが活発になった。2005年にセンターの事務室が開かれ、2007年に現在の場所に移転した。最近は、介助者との関係性が課題になっている。(以上は12月17日ティラワットからの事務所での聞き取り、筆者、通訳、ナンタ同席による)
事務局長のナンタは会計と運営の中核を担っており、介助サービスの調整とそこで起こるトラブル処理、職員の人事管理をおこなっている。ティラワットが大きな方針を出し、行政との交渉を行ったり、他団体との調整を担っている。ナンタも2002年から2004年のJICA研修をティラワットと一緒に受け自立生活の理念を共有している。
若手の職員として頚髄損傷の四肢麻痺者Bがおり、彼はコンピュータグラフィックや会計、事業報告などを行っている。事務局を支えるメンバーとしてポリオの歩行障害を持つTがおり、会場での参加者の受付や名簿管理、介助者のローテーション表など細かい事務作業を的確にこなしている。
ピア・カウンセラーとしては20代前半の脳性まひで電動車いすに乗ったAが中心で、親との関係が悪かったのがいまではとても良い関係になっており、地域の人たちにも広く受け入れられている。ピア・カウンセラーとしてはもう一人全身やけどを負って肢体不自由で車いすに乗ったOがいる。
現在ソウソウポウ[6]より2006年に130万バーツ、2007年に160万バーツ(1月あたり約70万円)の資金を受けており、事務所の運営管理費と介助サービス、プログラム実施費用、移送サービスなどの資金として活用されている(12月23日事務所にて聞き取り、筆者、通訳、ナンタ同席)。
一方、同じ県内にあるプッタモントン自立生活センターは2007年にサンティを中心に、ナコンパトムのセンターが遠距離で通いきれないので、プッタモントン郡のサラヤ村に作られた。所長のサンティは2003年から2005年、タイAPCDの自立生活研修に参加しピア・カウンセリングを中心に学んだ。特に2006年には日本での集中ピア・ピアカウンセリング講座を受け、リーダーとして独立していける力を身につけた1人である。
ナコンパトムとプッタモントンの2つの自立生活センターは密接に協力し合って運営されており、タンボンで自立生活セミナーを開催する場合には両方のセンターから講師を出して運営し、職員の送迎についても1台の車を共有しあうなどしている。プッタモントン周辺にも数十名の障害者がおり、毎月4回のサポートグループ[7]の開催、10回の個別相談を受けるなど、地域活動は非常に活発である。現在プッタモントン自立生活センターの事務所はサラヤタンボンにあり、ナコンパトム自立生活センターとは幹線道路を8キロ離れたところにある。現在身体障害者の女性2名と視覚障害者職員1名、それに健常者で運転手も兼ねた男性職員が1名いる。政府の外郭機関であるソウソウポウから一年間で150万バーツの寄付を受けて運営されている。その資金で事務所の運営費、職員給料、介助者の雇用、プログラム実施費用などがまかなわれている(以上12月19日プッタモントン自立生活センターにて聞き取りより、筆者、通訳同席)。
第2節 ナコンパトム自立生活センターを自立生活センターたらしめた要因
調査の目的として特に重点をおいて調査した4つの点「自立生活センター設立・運営のプロセス」「5つの要素」「エンパワメント」「社会の変革」について、所長、事務局長、非障害者職員、障害者職員、介助者、サービス利用者、障害者の親、地域住民、行政職員のそれぞれがどのように自立生活センターを評価しているのかをまとめ、分析に備える。
ナコンパトムのセンターが自立生活センターとして成立しているというのであれば少なくとも以下の5つの指標において実質的にその組織体制や行動している内容、サービス提供の実態などを聞けば、その指標が満たされていることが客観的に確認できるはずである。途上国においてこの5つの指標を満たすことは、国内では他にモデルがない中で達成しなければならないというハンディがあり、宗教的文化や大家族制度、伝統的な障害者に対する考え方から難しいことは最初から予想されていたことではある。それでは1指標ずつ順を追って確認していくこととする。
指標1「運営委員会の過半数と代表・事務局長が障害者であること」
ティラワットはナコムパトム自立生活センターの所長である。彼がどのようなプロセスや関係性の中で自立生活センターの所長となり、現在の代表事務局長に障害者が就任し、運営委員の過半数が障害者であるという体制を作り上げたのか、それは自立生活センターの基本条件を満たしているのであろうか。
ナコムパトム自立生活センターの体制は、運営委員の9割が障害者であり、代表は頚髄損傷の四肢麻痺者であり、24時間の介助を必要とする。事務局長のナンタは脊髄損傷で身の回りの事はできるが、移動外出や外出時のアクセスが悪い場所でのトイレなどの身辺介助が必要となる。
なぜティラワットが代表になったかを知るにはタイの障害者運動の歴史をたどらなければならない。
ティラワットの自宅で食事をしながら聞き取りを行った。同席したのはティラワットの介助者である弟、ナンタ、筆者とその介助者、通訳の6名である(2007年12月23日)
「1994年から2000年まで、ナコンパトムには障害者関係のサービスや情報が何もなかった。私はチュラロコン大学のラグビー部で練習中に、障害者になった。私は1994年に今後のことを考えるなかで、法律等を勉強し、どうすればよいかを考えた。その頃約10人の障害者が集まり、私が中心となってナコムパトム障害者協会が設立した。」
このようにティラワットはタイの東大と言われるチュラロンコン大学の在学中に事故に遭ったという経歴から、自然にグループ内のリーダー役を務めており、その際、障害の重さは何ら問題ではなかった。現在の事務局長ナンタはティラワットに全幅の信頼をしている。
それではなぜ彼が権利擁護的な従来の障害者運動団体に見切りをつけ、自立生活センターに惹かれるようになったのかをみてみよう。
上院議員も務めたタイDPI会長のナロンは、士官学校の学生時代にリュウマチで障害者になった人で、タイの障害者運動の創始者である。ティラワットはナロンと一緒にリハビリテーション法を1900年に成立させるための運動を行った。その結果、法律はできたが、自分たちの生活は何も変わらなかったことをティラワットは経験した。その頃パタヤで自立生活セミナーを受講し、自分が変わり社会を変えていく自立生活運動を知り、参加するようになった。という。
次に、事務局長のナンタに聞いてみた。面接は、彼の事務所にて。同席者はティラワット、筆者と通訳者である(2007年12月17日)。
筆者「どうして事務局長に選ばれたのですか。その過程でどのような葛藤がありましたか。」
ナンタ「障害者の手伝いをしたかった。また、口がうまい。人の話を良く聞いたり、調整能力が買われた。そういう人材は当時あまりいなかった。」
以上で見るように代表と事務局長は共に障害者であり、とくに代表は重度の障害者であることがわかる。
次に指標の中の運営委員の過半数が障害者であるという箇所についてみてみよう。ティラワットは2002年から2005年までAPCDの研修と日本での研修を済ませており、彼が設立した2005年には自立生活センターの51%要件についてはよく知っていた。
ティラワット「運営委員9人のうち2人は非障害者である。開設当初は、障害者だけ10人だった。その後6人となり、現在は9人になっている。9人になったときに、健常者2人が入っている。障害者が多いことで今のところデメリットはない。あえていうなら会議時間がかかることぐらい。メリットは障害者問題がよりクリアで深い理解が容易である。そのこともあり、会として選択をするときに後でよいと思う判断をすることが多い。例えば、ある障害者に対する病院の対応が良くなかった。皆で押しかけた。もしも運営委員が非障害者のみならばこの行動は理解されなかった。健常者運営委員の2人は自己決定の理解はあるが、権利擁護の理解はない。健常者の運営委員は語学校とコンピュータの先生である。」(2007年12月17日、事務所にて聞き取り。同席者はナンタ、筆者と通訳)
運営委員についても過半数が障害者であり、運営委員が過半数である意味についても、運動の中で実体験をしていることが聞き取りからわかった。以上から、指標1を満たしていることが確認できた。
指標2「ピア・カウンセリング、自立生活プログラムをおこなっていること」
ここでは障害者の自立のために役立っているという当事者自身によるピア・カウンセリングと自立生活プログラムについて、それをナコンパトム自立生活センターでは誰が、どういう手法で、どのくらいの回数で、誰に対して行っているかを調査した。
①ピア・カウンセリング
ナコンパトムのピア・カウンセラーの中心は、ティラワット、サンティ、ナンタ、職員A,Bなどである。とくにティラワット、サンティ、ナンタの3名は発足当初からピア・カウンセリングと自立生活プログラムにかかわり、APCDの7年間の研修とそれぞれ各人が日本に来て受けた1週間の集中ピア・カウンセリングコース(ティラワット03年、ナンタ04年、サンティ06年)を受けている。基本的な理念の理解と講座のリーダーを行う技術をマスターしており、日本のピア・カウンセラーに劣らない高度なピア・カウンセリングを行っている。
タイにおけるピア・カウンセリングは、2003年1月にパタヤのレデンプトリスト障害者職業学校において、日本からの講師2名が1週間にわたって基本コースの研修を行って初めて導入された。その際にナコンパトムからは、ティラワット、サンティ、ナンタ、A、B、C、Kが参加した。このころティラワットは自宅で開店しているスーパーマーケットの会計と在庫の管理係をし、サンティは闘鶏場を経営しており、それぞれ自分の仕事が忙しい中での参加であった。
表4-1 ナコムパトム自立生活センターのピア・カウンセリング講座参加状況
|
氏名 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| Mr. Teerawats Snipatomsawad |
○ |
○ |
○ |
|
| Ms. Nanta Songpeenong |
○ |
○ |
○ |
|
| Mr. Santi Rungnasuan |
|
○ |
○ |
○ |
| Mr. A |
|
○ |
○ |
○ |
| Ms. C |
|
○ |
○ |
|
| Mr. B |
|
|
○ |
○ |
| Mr. K |
|
○ |
○ |
|
2002~2005年JICA「障害者の自立生活研修計画報告書」より
(注)2002年は初年度でピア・カウンセラーになる候補者を選ぶための自立生活プログラムを行ったのみなので、実質的にピア・カウンセリングをおこなったのは2003年からである。
2003年の時点ではタイでピア・カウンセリングのリーダーを務めることができるのは、2003年の日本でのピア・カウンセリングの研修を受けたノンタブリのマイとナコンパトムのティラワットであった。彼らは2003年~2005年まで3県で現地の障害者団体と協力してピア・カウンセリング講座を実施し、その講師を務めた。
2004年3月に開催されたAPCDのピア・カウンセラー・リフレッシャーコースにおいて、講師から各ピア・カウンセラーは地元に戻ってからピア・サポートグループを開催することが提案された。各県でピア・サポートグループが実施されたが、特に熱心にこれを実施してきたのがナコンパトムの自立生活センターであった。
ナコンパトムの自立生活センターでは、日本の講師たちに教わったピア・カウンセラーたちが地域で暮らす障害者のメンバーにそのピア・カウンセリング技法を使ってピア・サポートしている。
ピア・サポートには3種類の方法がある。第1は個人の家を訪問して、1対1のセッションを行うものである。これは月に10回程度行われている。
第2は自立生活センターの会員となっている障害者メンバーのうち15人前後が、月に3、4回のペースで公園や集会場に集まり、主題を決めて行うグループセッションである。時には知り合いの別荘を借りて泊りがけで行われたりもする。参加者は在宅訪問で知り合った障害者とか、これまで外出したこともなかった障害者、また普段から自立生活センターによく訪れている人たち、開催地の近くに住んでいる障害者たちなどである。このタイプのグループはお互いに既に顔見知りで、自らの深い悩みや心の傷を話し合える関係ができあがっており、話される内容もテーマに沿ってかなり深刻な家庭の事情や介助者の不足の問題、金銭的な悩みなどピア・カウンセリングでなければ言えないような問題にわたっている。
第3のタイプは、まだ自立生活センターのないタンボンでその長と話し合って障害のある住民の名簿を借りて、その全員をOBT事務所の庭などに集めておこなうものである。その場合、昼食をふるまって、丸一日かけてグループでのセッションをおこなう。中には家から一度も出たことがない人や、他の障害者に一度も会ったことのない障害者もおり、家族が相手にしてくれなかったり、移動の手段がなくてOBTに障害者手帳の申請にも行けない人たちが、自立生活センターやOBTが差し向けた車で集まってくる。そこで各人の現在困っていることや悩んでいることを話してもらい、グループを形成するきっかけを作るとともに、みんなの要望を聞き取ってOBTに障害者全体の要望書として提出し、OBTに障害者サービスの改善を求めていく、というものである。
その他のプログラムとして、リーダー養成のためのピア・カウンセリングのセミナーがあり、2ヶ月に1回開催され、1回のセミナーで10名程度が参加している。
②自立生活プログラム
自立生活プログラムはピア・カウンセリングに比べて低調であると言える。その理由は、タイではまだ実際に親元から離れて一人で暮らしている障害者がほとんどいないことよる。ティラワットなどリーダーたちは一人暮らしを最終ゴールとして考えているが、実際彼自身も親元におり、部屋は独立しているものの経済的には家族と一体化している。そのような状況の中では、精神的なエンパワメントを主たる課題とするピア・カウンセリングは、全体で共有できるプログラムではある。一方、自立生活プログラムは、自立生活の2年以上経験のある自立生活のエキスパートが後輩たちに障害を持って地域で暮らしていくための生活技能を伝えていくものである。具体的な自立生活から得た技能を伝えられるリーダーが今のところおらず、またそれを求める利用者もいないことが、低調の原因となる。
プログラム化された具体的な自立生活プログラムは、調査期間中には実施されていなかった。しかしそれに近いものとして、公園で参加者が口で筆を使って絵を描く方法を講師から教わったり、その完成した絵がセンターに展示されて運営費の一部となったりするなど、自分でも何かができるという自信を障害者にもたせるきっかけとなる活動がある。外出では買い物に出たり、公園に行ったりしている。
以上で見てきたように第2の指標であるピア・カウンセリングは十二分に行われ自立生活プログラムも多少ではあるが実施されていることが確認できた。
指標3「介助サービスを提供しているか」
ここでは、①ピア・カウンセリングを終了した障害者がなぜ介助サービスを求めるようになるのか、②介助サービスが始まる前の状況、③自立生活センターの介助サービスの現在の実態、④自立生活センターの介助サービスの制度と体系、⑤介助サービスの利用者の声、⑥介助者の声、⑦行政の声、について調査して、第3指標の成立状況を分析する。
①ピア・カウンセリングを終了した障害者がなぜ介助サービスを求めるようになるのか。
ピア・カウンセリングで個人のエンパワメントを果たした障害者は、外へ出て社会に参加する事を考え始める。介助サービスはそのときの大きなツールである。自立生活センターでは家族介助以外の介助者によるサービスを受ける事を利用者に薦めており、ボランティアベースでのサービスから、行政の外郭団体からの補助金による運営資金を使ってのサービスへ移行しつつある。
②介助サービスが始まる前の状況
さて利用者は介助サービスが始まるまでどのような生活をしていたのであろうか。利用者Cと利用者Rの例を紹介する。
筆者の「介助サービスについてどう思う?」という質問に対して、Cは「いいと思う。家族がいても自分を理解してくれる介助者に会うとうれしい。介助者がいると両親が介助をしなくていいから」とこれまで家族には気兼ねしながら介助を頼んでいた様子を話してくれた。さらに「家族と介助者とどっちがいい?」という質問に対しては、Cは「車の運転などでも介助者がいると母が楽。もっと長時間来てくれるといい。」とこれまで車の運転などでも家族に負担をかけ、長時間の介助は頼みにくかったようである。Cは家族介護の問題点を話してくれた。
Rは介助サービスが始まる前の状況をつきのように語っている。「事故にあってすぐは暗かった。普通の生活ができないから。自立生活プログラムを知っても外に出て行く気にはならなかった。自分には何もできないと思っていた。昔は姉に手伝ってもらった。今では母も歳をとってきた。家族だと気持ちを前に出してけんかすることもできなかった。自立生活センターの介助者をつかうようになって気持ちの整理ができてよくなった。気持ちの表現も工夫している。外にも気兼ねなく出て行ける。このような生活を続けていきたい。今は姉も手伝いに来ないが姉も元気である。僕の決めたことに口出ししなくなって。自己決定に介助者を使うことはいい。」
Rも、介助者だと気兼ねなく出かけられることや、姉に介助を依頼しなくて済んでいるために、姉はRの自己決定に反対しなくなった、というメリットを挙げている。
Eは、介助者を使う前の家族との葛藤を次のように語っている。「介助者はまだあまりつかってない。外に出て行けるかどうかは家族次第。妹も僕に親切でない。例えば、水浴びをしたい時に、妹の機嫌が悪いと、水をぶっかけられたりする。介助者を使えば妹も変わると思う。介助者には自分のしてほしいことをしてもらえる。」
Eの場合は深刻である。妹の介助を受け虐待に近い状態になってきていた。介助サービスが始まる前の障害者の状況はかなり悲惨なものであった。彼が介助サービスを使うようになれば、きっと家族との関係も変わっていくことだろう。
③ 自立生活センターの介助サービスの現在の実態
ナコンパトムの自立生活センターの職員はその多くが日常的に介助を必要としている。所長のティラワットは両手・両足がまったく動かないため、食事やトイレなど、日常生活のすべての面にわたって介助が必要である。ピア・カウンセラーのAは、やはり食事介助やトイレ介助が必要な重度の脳性マヒの障害を持っている。会計を手伝っているBは頚髄損傷で、衣服の着脱やトイレなどの日常生活上の介助が必要である。現状では公的な介助サービスが制度化されていないため、事務所の中では職員の介助に頼り、家庭では家族が介助を行っている。
利用者のRは「昔は姉に手伝ってもらっていた。家族だと気持ちを前に出してけんかすることもできない。自立生活センターの介助をつかうようになって気持ちの整理ができてよくなった。気持ちの表現も工夫している。外にも気兼ねなく出て行ける。このような生活を続けていきたい」と述べており、自立生活センターを始めてから、介助は家族に頼るべきものではないという意識がしだいに職員や利用者の中に芽生えてきている。(12月22日R自宅にて聞き取り、筆者、通訳、ESCAP職員)
2007年10月より、ソウソウポウの補助金が入ってきたことにより、介助サービスが始まっている。利用者は以前とは違って、職員や会員だけでなく、外部の人たちもいる。月に150時間を上限としているが、それ以上必要な人は今のところいない。
介助者の質を高める研修もしているとは言うが、介助者に聞くと研修は受けていないという人もいたので、組織的にはやれていない状況であろう。
これまでは家族が介助者となるケースが多かった。しかし、現在の10人の介助者は、家族以外の人という条件で募集している。学生ボランティアも活躍している。2001年からセンターに関わっているWは、今は職員で4年間介助をしている。
④ 自立生活センターの介助サービスの制度と体系
2007年12月17日ナコムパトム自立生活センターにてティラワットとナンタから聞き取ったものをまとめた。筆者のほか、通訳同席。
タイの自立センターにおける介助サービスは、ナコンパトム自立生活センターで2007年9月から2008年3月までの間、ソウソウポウの支援で実施されたのが始まりである。
ナコムパトムのセンターでは2008年度8ヶ月分の補助として170万バーツを受け取っており、プッタモントンの自立生活センターでは同期間に150万バーツをソウソウポウより受託している。それぞれ職員2名分の給料と家賃として使われている他、協同で10名の介助者を雇っている。現在、両センターとも介助サービスは1時間あたり50バーツで行っている。
現在ナコムパトムとサラヤの自立生活センターでは、平等に使えるように1ヶ月間に1人が使える介助サービスの上限時間を原則として150時間としている。
ナコムパトムの自立生活センターの介助者数は10人で、利用者数は14人、コーディネーターは2人である。このコーディネーターの1人はナンタであり、もう1人が健常者である。介助サービスについてはサラヤの自立生活センターと合同でやっている。介助者は1日最長6時間働き、その収入は1日で300バーツ(900円)である。
一般の利用者の介助料の支払いは、障害者が50バーツを支払い、事務局が介助者に50バーツ支払うという形で、事務局の運営経費は介助利用料には転嫁されない。
ナンタに介助サービスはどのように自立生活運動に貢献したのかと聞いたところ、「はじめたばかりでまだ分からない。問題が山積である。特に利用者と介助者との問題が大きい。利用者は皆介助者に気を使っている」と介助者を使う事にまだなれていない利用者が多く、介助者に気兼ねしながら用事を頼んでいるようである。
ナンタによると家族が介助者を受け入れられないというケースもあるようだ。また、障害者自身が介助者に受け入れられているかどうか不安であったり、場合によっては介助者が怖いと言うケースもあるという。介助者の使い方、位置づけがよく分からないという利用者がいたり、介助者もどうしていいかよく分かってない場合もある。問題が起こったとき、介助者の理解不足が原因であることが多いという。
これらほとんどが介助者を初めて使う事からくる困惑や不安である。自立生活センターの役割は利用者と介助者の双方の不安や戸惑いを取り除いて、両者の間に良い関係を作れるようにコーディネートすることである。コーディネーター自身の力量や、利用者・介助者の理解が、この点ではまだ十分でないことが観察される。
⑤ 介助サービスの利用者の声。
介助者がどのように使われているか、その利点や今後の期待などについて利用者は以下のように言っている。
利用者Pは、「家では弟に手伝ってもらい、外に行くときに介助者をつかってる。それだけでも感謝している。介助者をつかえば自分の能力を発揮できる」と自宅での介助がまだ介助者に頼めないが、以前より外出できるようになっただけでも大きな変化を感じているようだ。(12月18日ピア・サポートグループでの聞き取り。筆者、通訳、ナンタ同席)
利用者Iは15年間自宅で寝たきりでいた。筆者が介助者のいなかったときの生活の様子を聞くと、以前は73歳の母親がシャワーをやってくれており、母の体が心配だった。父親は75歳で息子が障害者になったことに違和感があるようで、介助はやりたがらなかったという。自立生活センターと知りあって介助サービスを使えるようになって生活が一変したようである。「外に出てこられるようになった事はほんとにうれしい。車椅子に乗れるのは介助者が来てくれる時だけである。母だけでは移乗が難しい。体が大きいので介助者2人でやってもらっている。今日の介助時間は10時から15時までである。週2回でも外に出れるのはうれしい」。(12月22日利用者聞き取り、利用者Iの自宅で聞き取り、参加者ESCAP職員、Iの介助者兼運転手、筆者と介助者、通訳)
親の高齢化により、自宅での介助が受けれなくなった障害者は自立生活センターの介助サービスは使えるようになって、車いすへの移乗や外出が出来るようになったことを喜んでいる。
利用者Kは、一歩進めて自立生活を希望し始めたようである。「本当は地域の中で暮らせるといいが、5、6人が手伝ってくれればできる」と具体的な自立生活のイメージを語ってくれた。「政府がやってくれたら、そしたら僕らも出て行ける。介助者の助けで外にいける・訓練できる。でも介助者が今は見つけられない。車椅子を誰が押してくれるのか。OBTに行くにも介助者がいなきゃできない。でもこっちから地域の人に助けを求めて政府に行けばほらこうやって助けがあれば外出できるといえる」と政府の公的な介助サービスの制度化を求めている。(12月18日ピア・サポートグループの聞き取り。筆者、通訳、ナンタ同席)
ナコンパトム自立生活センターにおいて、親から独立して介助サービスを使って完全に自立生活をしている人はいまだに1人もいない。Kが言うように、政府の介助サービス制度が始まらなければ、5人から6人の介助者のローテーションは作れない。家族は既に一定程度介助サービスに依存をし始めているが、いまの介助サービスは停止されればもとの状態に戻ればよいと考えてサービスを使っている。親からの独立生活に親も本人も安心して乗り出すためには、公的な介助サービスの開始が前提である。その場合、当面家や生活費については家族に依存することになるだろうが、それは新たな生活実態を生み出すことになり、政府への制度要求につながるニーズの顕在化であり、自立生活運動の望む結果でもある。
利用者Cは、具体的な介助サービスのシステムを考えている。「介助者サービスはOBTがやってくれるといい。両親がいるのになぜ介助者という人もいる。でも介助者を使って外に出ることが大事である。行政の職員が家に来て、介助の必要性を調べてくれて支援してくれたらいい」と介助サービスの提供は自立生活センターではなくOBTがやるとよいと述べた。これは彼女の家がナコムパトムの自立生活センターからは遠く、介助者が通ってくるのが難しいと考えているためである。
介助の利用者の中には介助者との関係がうまく作れない人もいる。特に言語障害がある障害者の場合、その調整にはかなり苦労するようである。
利用者Aは、毎日、朝1時間、夜2時間、トイレ食事着替えなど生活全般で介助を利用している。彼は介助者との関係について、次のように言っている。「自立生活センターでは、1日か2日の介助利用者研修を行う。しかし介助者との関係は難しい。問題があったらまず介助者と話す。ダメならセンターに言う。傷ついていたらピアカンをやって気持ちを落ち着けてから再度介助者と話すなどしている。他のやり方として、長時間介助者を使っている同士で話し合ったりする。それでも解決しないときには、介助者を変えてもらうこともある」という。自立生活センターでは介助者の調整の他、介助者とのトラブルについても相談にのっている。(12月24日事務所にて聞き取り。筆者と介助者、通訳)
介助サービスのシステムについては一応コーディネーターが2名あたっているが、システムとして機能しているのであろうか。利用者のKに聞いてみた(Kは45歳。12月24日事務所にて聞き取り。筆者のほか、介助者、通訳が同席)。
筆者の「介助を使いたいとき、誰に頼むの」という質問に対してKは、「ナンタに頼む。いつも断られる事はない。電話すればナンタがいなくても他の人にも頼める。依頼は前日でも大丈夫で、早めに連絡しろなどとは言われたことはない。介助者はセンターから派遣されるのに任せており、現在数人を使っている」と答えている。
介助サービスの規則は今のところなにもないようである。利用人数が少ないので予約をしなくても使えているが、利用者数が増えるとこのような方式ではやっていけないであろう。いまは利用者の信頼を勝ち得る事に重きがおかれ、システマティックな介助サービスが目指されているわけではないようだ。
⑥ 介助者の声
まず12月22日、Iの自宅にいる介助者Qに聞き取りを行った。
筆者の介助者を始めたかのきっかけは何かとの問いに介助者Qは「前はタクシーの運転手をやっていた。その頃から社会貢献をしたいと思っていた。サンティさんに会って、彼の家の近くにいる介助利用者を紹介してもらった」と職員との個人的なつながりで介助を始めたようである。
給料のことについて聞いてみた。「運転手をやっていたときよりも安くなったが、この仕事のほうが自由があってよい」。次に、自立生活センターで働く意味について理解しているかを聞いてみた。介助者Qは「自立生活センターの自己決定の理念は理解している。つらい部分はない。トラブルも特にない」と答えてくれた。利用者Iの目の前での会話であったために、お世辞も多分にはいっていたであろうが、自立生活センターでの介助サービスの持つ意味については介助者も理解しているようであった。
次に12月24日、専従職員Wから事務所にて聞き取りを行なった。ナンタ、筆者と通訳が同席した。Wは2006年から専従介助職員として自立生活センターに勤めている。筆者は「介助サービスは自立生活センターにとってなぜ必要か」とWに聞いたところWは「介助者がいることで外出したり、家に中で用事をしたり自由にできるので、絶対必要だと思う」と自立生活センターにとっての介助サービスの重要性を理解していた。
介助者と家族のトラブルは特にないという。次にWに「介助者として自分が役立っていると思うときは何か」を聞いてみた。「障害者が介助によって快適に過ごしていたり、仕事できていたりするのをみて介助サービスが役立っていると感じる」と介助者としての生きがいを感じているようすが伺えた。
筆者は「介助の記録をとったり、定期的なミーティングはやっているか」を聞いてみたところ、Wは「センターの会議はやっているが、介助の会議は特別にやっていない。介助に関する日誌などはない。介助の依頼はすべて電話で受け付ける。介助者の遅刻や日にち間違えなどはよく起こっている。改善に向けた話し合いなどは今のところない。派遣の記録は一応残している」と答えた。
そばに介助サービスの責任者ナンタがいたこともあり、かなりフォーマルで好意的なコメントをしているように思える。しかし、ミーティングの回数など実態については率直な意見が聞けた。(12月24日 専従職員W、事務所にて聞き取り、ナンタ、筆者と通訳)
介助サービスは動き始めたばかりで、まだシステム的な運営がされているとは言いがたい。これからも利用者や介助者から苦情がたくさん挙げられていくなかで、次第にサービスも改善し、定期的な会議の開催や記録の保存など形を整えていくことだろう。ソウソウポウの支援は期限付きではあるが、5年以内に制度化される見込みを所長たちは持っているようである。幸い「障害者の生活の質の向上法」ができたことにより加速度的に介助サービスの制度化も進む事と思われる。ともかく指標3の介助サービスは実施されている実態が確認できた。
指標4「障害種別を超えてサービスの提供をしているか」
ここでは自立生活センターがなぜ障害種別を超えてサービスを提供している必要があるかについて以下の項目順に調査結果に基づいて報告する。①障害種別を超える事についての自立生活センターの実態と考え方。②行政の受け止め方について。
① 障害種別を超える事についての自立生活センターの実態と考え方
障害種別を超える事についてサンティに聞いてみた(12月24日ブッタモンドン自立生活センターにで、筆者、通訳聞き取り)。
サンティは「最初から全ての障害者を対象にしたいと思っていた。」と言う。彼は当初から受け入れを視野に入れていた。そこで筆者は、講習会には聴覚障害者の人達の参加も認めるのが聞いてみた。彼は「勿論受け入れる。それもあって手話講習会にVなど聴覚障害者が参加した。」と講習会でも障害種別を越えて参加の呼びかけが行われている事がわかった。
次に筆者は障害種別を越えて自立生活運動を推進する動機は何か?行政からの資金提供を受けるためなのか?」と聞いてみたところ、彼は「地域の活動の中で色々な障害を持っている人が参加すべきだと考えていることは動機の1つだが、それを始めたのは自分自身の意思だ。自立生活センターの設立要件どうこうではない。発想として障害種別を問うということがタイの自立生活センターにはない。」とサンティは障害種別を越えて運動を進める事はタイの障害者の文化に根ざしたことだと述べている。
次に同席していた視覚障害者の職員Wに「自立生活センターは視覚障害に親切でない面があるのでは?」と所長のサンティがそばにいるので彼が答えやすいように否定的に聞いてみた。するとWの答えは「そう思ったことはない。色々な話をしあえるので、障害種別を問わないことは自分にとってもいい。」と肯定的に答えた。視覚障害者にとっても自立生活センターは暮らしやすい場らしい。更に職員Wと一緒にいた視覚障害者の女性に聞いてみた。彼女も自立生活センターの理念に賛同しており、盲人協会のメンバーとして白杖などを買ったり、併設の点字図書館を利用したり、イベント参加の目的では盲人協会を利用している。筆者「あなたにとって自立生活センターに通うメリットは?」と聞いたところ彼女は「こちらの活動の方がずっと進んでいる。盲人協会は視覚障害者のみを対象としているがここらは障害種別を越えているから。」と障害種別を越える運動の有効性を視覚障害者の立場からも支持していた。
このように自立生活センターに参加している視覚障害者と聴覚障害者がともに自立生活センターの障害種別を越えての活動を評価している事がわかった。よって第4の指標である自立生活センターは障害種別を越えて活動している事が十分確認できた。
所長のサンティは障害種別を越えて運動を進めることのメリットを次のようにまとめている。
・ 他の障害者を受け入れることで、その障害についてよく分かるようになり、しいては社会における障害者のこともよく分かるようになる。
・ 障害種別を越える事が地域のあらゆる障害者にとってより良い方向への変化につながる。
・ 職員や介助者が手話を覚えれば視覚の人にもサービスを使いやすくなる。そのような形でセンターのサービスの質が良くなるだろう。
② 行政の受け止め方
以下は、12月18日タンボン長WにOBT事務所のタンボン長室にて聞き取りしたものである。ナンタ、筆者と介助者、通訳が同席した。
筆者「自立生活センターの障害種別を越える活動についてどう思いますか。」
村長W「行政は高齢者と障害者の問題を対象としている。最近法律が変わって、障害者の生活の質の向上がキーとなっているのでOBTとしても支援しやすくなっている。全種類の障害者を支援したい。全体の障害者を考えるのが行政の役割だと思っている。」
村長は、在職4年5ヶ月。残りの任期は7ヶ月。再任されるかどうかは不明だという。経験豊富な村長なので重ねて村の建築上のバリアフリーについて聞いてみた。「村のバリアフリーについては、スロープは新しく建設するところである、障害者からの要望があるところなどに限って行っている。建物のバリアフリー化は一ヶ所で10万バーツ以上かかるので実施がなかなか難しい。必要な場所・要望のある場所から改善している。そのためには当事者の人にも意見を出してもらいたい。」と積極的な返事がかえってきた。更に村長は「しかし、聴覚と視覚、そして身体の各障害者の設備投資はちがう。どこか一箇所となると「何でここはやらない」と他の地域からも苦情が出るので、バランスを考える必要がある」と、村に置いても障害種別を越えてサービスを提供している事がわかった。
「現在の庁舎は建て替えるときはトイレなどもアクセス化されたものを導入したい。呼吸器をつけた障害者が病院にいて支援を求めている。ナンタの応援を頼みたい」とその場で支援を求めており、このような場面からも自立生活センターが行政に頼られている。
障害種別を越える運動について村長も理解があるようで、自立生活センターが障害種別を越えて支援をしている事が確認できた。
指標5「重度障害者がサービス利用者になり、また運営に参加しているか」
所長のティラワットやサンティ自身は介助が必要な四肢麻痺者であり、重度障害者である。そのためサービス利用者として同等の障害または言語障害もある重度障害者も対象となっている。
在宅訪問やピア・カウンセリングやピア・サポートなどの参加者もほとんどが重度障害の四肢麻痺者であり、事務所に飾ってあるメモ全て彼らが口で筆を咥えて書いたものであり、利用者のほとんどが重度障害者である。
運営委員も、健常者2名とナンタを除けば、全て介助が必要な重度障害者である。ティラワットとサンティは共に日本のヒューマンケア協会(八王子)での研修を10日間以上受けており(それぞれ2003年、2005年)、そのため重度障害者が代表・事務局長を務め、運営に参加することが当然であるような認識をもっている。このことはナコンパトム自立生活センターの規約の中で義務付けられているわけではないが、当然のルールのようになっている。
ナコムパトムの自立生活センターの事務局長は両手が効く脊髄損傷のナンタではあるが、彼女も車椅子に乗っており移動の時などには介助が必要で、重度障害者の範囲に入る人である。彼女はその運営能力を買われてティラワットから請われて事務局長になったのであり、ティラワットの指導の下で忠実な事務執行者として重度障害者の心からの支援者である。これは、以下のような介助サービスの苦労話の中でも明らかであった。
筆者「あなたにどんな相談がある?」
ナンタ「介助者や家族との問題などについて相談が来る。たとえば、介助者の探し方、質の悪い介助者との付き合い方、質をどう高めるか。コミュニケーションの問題や、遠慮して上手く自分の気持ちを介助者に伝えられない障害者も多いので、その相談も多い。」
(12月17日、事務局長ナンタの事務所にて。ナンタ、ティラワット、筆者と介助者、通訳が同席)。
まとめ
まず第1の指標である「運営委員会の過半数と代表・事務局長が障害者であること」については、運営委員会はナコンパトム自立生活センターとプッタモントン自立生活センターで共通の委員会になっており、現在9人のうち7人が障害者であり、委員会での決議事項も当事者のニーズを優先する結論を出せる当事者主導の運営委員会が形成されている。代表のティラワットは二つの自立生活センターを統括するリーダーとして事務局長のナンタや職員からも信頼を受けており、サンティは新しいプッタモントンの自立生活センターの所長としてピア・カウンセリング事業を行政に認めされるまでの力を持っており、ティラワットの元で運転手や車を共有してもらいながら協力関係を持って運営の中枢を担っている。このことによって、代表・事務局長は実質的な意味でもその職責を全うしている。
第2の指標である「ピア・カウンセリング、自立生活プログラムをおこなっていること」については、ピア・カウンセリングのリーダーも4名養成されており、月に10回以上の個別カウンセリングと、ピア・サポートグループが月に3、4回のペースで公園や集会場に集まり行われていた。このことから障害者自らが積極的にピア・カウンセリングを日常的に行っており、生活に根付いた当事者エンパワメントのシステムとして定着していることが調査から確認できた。またピア・カウンセリングによって個人のエンパワメントが障害の社会モデルの気づきとなって、行政への要求運動につながっていることから、ピア・カウンセリングの本来の目的である社会変革への基盤づくりが進んでいるといえる。
自立生活プログラムについては調査期間中には実施されていなかったが、利用者が買い物などに外出するプログラムや口で筆を使って絵を書く自分の能力を発掘するためのプログラムが行われていたが、日本で行われるような自立生活体験室での調理や介助者を使っての自立生活の実体験プログラムなどは、自立生活体験室がなかったり、親から離れての一人暮らしがまだ現実の課題となっていないために低調である。
第3の指標である「介助サービスを提供しているか」については、家族介護に依存してきた障害者たちは、自分たちの本来のニーズは介助者と外出したり、気兼ねなく日常生活上の介助を受けることにあると気付き始めた。最初は介助者をどう扱っていいか不安だった家族や当事者はしだいに介助を使って生活をする楽しみや気軽さを享受して、必要なサービスとして介助を位置づけるように変わってきた。この顕在化したニーズに応える形で2007年にはソウソウポウの支援で、モデル事業としての介助サービスが始まっている。月に150時間の上限はあるものの、障害者の日常生活は介助者を使うようになってから画期的に質が向上している。いまだにモデル事業という位置づけで不安定なために、家族も本人も自立生活センターの介助サービスの継続性に不安を感じており、介助を使っての一人暮らしに踏み出すものはまだいない。しかし、利用者の中には介助サービスが制度化されれば、一人暮らしをしたいという希望も顕われ始めている。
第4の指標である「障害種別を超えてサービスを提供しているか」については、サンティの言葉にもあったように、タイの文化においては障害種別を超えることは当然の前提となっており、発想として障害種別を問うということがない。二つの自立生活センターでも視覚・聴覚障害者がすでに職員や利用者の中におり、自立生活センターが多様な障害者を包含するものとなっている。
最後に第5の指標である「重度障害者がサービス利用者になり、また運営に参加しているか」については、二人の代表とも頚髄損傷の四肢麻痺障害者であり、日常的に介助を必要とする重度障害者である。利用者の大半は四肢麻痺者であり、介助サービスのニーズはほとんどの障害者に共通である。サービスの担い手がサービスの利用当事者であることは、自立生活センターのサービスの質を保障するものとなっている。
以上で、第1から第5の指標までの全ての指標において、ナコンパトムとプッタモントンの二つの自立生活センターは有効に機能しており、途上国でも自立生活センターが設立しうる事が確認できた。
第5章 障害者のエンパワメントと社会変革
第4章で「途上国においても重度障害者が中心になって運営される自立生活センターが成立しうること、そしてそれを基盤として、障害当事者のエンパワメントによりニーズを顕在化し、福祉サービスの向上を促し、社会変革につながること」という仮設のうちの、「途上国においても重度障害者が中心になって運営される自立生活センターが成立しうること」が確認できた。
次に仮説の後半の「自立生活センターを基盤として、障害当事者のエンパワメントによりニーズが顕在化し、福祉サービスの向上を促し、社会変革につながること」を考察する。すなわち図2-2における個人のエンパワメントにより自立生活センターという組織ができあがり、自立生活センターを基盤として、本人のニーズがさらに掘り起こされ、そのニーズが集合されて自立生活センターのニーズとなり、社会変革へいかにつながっていくかをデータから確認する。
第1節 ナコンパトム自立生活センターの障害者のエンパワメントについて
本文ではエンパワメントの定義を「障害当事者が対等な対話を通じて自己の障害概念を定義しなおし、障害の原因を社会のありように求めて、その変革への行動を起こしていくプロセス」というようにした。本章では、パウロ・フレイレの「課題提起型アプローチ」による識字教育の構成要素として「対話」「気づき」「社会変革」の3つの側面に注目し、これらに対応して、対等なピアの対話がなされたか、障害概念が社会モデルに変化したか、社会変化への行動が始まったか、の3
つの指標を自立生活センターの支援においてみられるエンパワメントの要素と考える。これに照らしてナコンパトムセンターにおけるエンパワメントを検討する。
対等なピアの対話がなされたか
2007年12月17日、利用者Kへのインタビューをナコンパトム自立生活センターの事務所で行った。Kはピア・カウンセリングについて次のように語っている。「最初のきっかけは兄の友人が自立生活センターのピア・カウンセリングのことを知っており、紹介してくれたことにある。1年前にOBTで開かれたピア・サポートの集会に参加した。その前は家の中で過ごしていた。ピア・サポートはとても有意義だ。障害者同士で話ができ、過去の話などを共有できることは意義がある。自分のことを自分で決めていくというのは楽しい」。
Kの聞き取りから障害者同士の会話がピア・サポートグループでは行われている事が確認できた。しかし、これはフレイレのいう社会変革につながる「対話」にまではいたっていない。過去にあった障害者団体も障害者同士の会話の場はあった。しかし、障害者相互での高めあいがピア・カウンセリングのような形で、理論に基づいて構成されていたわけではなく、単なる慰め合いに留まっていたといっても過言ではない。ピア・カウンセリングでは社会モデルについても「気づき」や「障害の意識化」が行われ、エンパワメントしていく点がその後の「社会変革」を導く点が根本的に異なる点である。
ピア・サポートグループでは、現在自分の障害で困っていることについてピア・カウンセラーのリーダーが、参加者に意見を求める「対話」が行われる。例えば2007年12月16、17日の両日に渡り、ツングブア村でピア・サポートグループの集会が行われた。ここでは、「障害について」「家族について」という課題のもとに参加者同士が一対一でピア・カウンセリングを行い、10分ごとにカウンセラー役と参加者役とを交代しあいながら、自らの経験や気持ちについて話した。どちらが指導者というわけではなく、お互いの話し合いのなかで影響を受けあって、さらに会話が深まっていくと共に、共通にかかえる問題を社会変革につなげて行った様子は、まさにフレイレのいう「対等な関係での対話」が行われていたといえるものであった。
障害概念が社会モデルに変化したか
2007年12月22日、利用者Aへの聞き取りは筆者、通訳、ナンタ、Aの母親が同席し自宅で行った。
筆者は利用者Aに、自立生活センターと知り合って何が変わったかを聞いた。Aは「自己決定についてはセンターで習った」と答えており、自立生活センターの関与によってAは家族のなかにいても自己主張してもよい存在であることを自覚し、自己決定を自らやりぬくことを決心している。筆者はさらに「家族介助に対する別の視点を持ったか」と質問した。するとAは「(家族に対しての自分の態度は)変わった。知る前より自分の気持ちを言えるようになった。自分にも自己決定能力がある、障害があっても生活をコントロールできることは変わらない」と述べている。自分に自己決定能力があり、障害があっても生活をコントロールできるとの発言から、彼が「障害は個人の側でなく社会の側にある、という概念」への「気付き」を得たことがわかる。
同様に、2005年にAPCDが作成したナコンパトム自立生活センターについてのビデオによると、センター職員のBは、自立生活センターと知り合って自分がどのように変わったかについて次のように述べている。「家から出て自立生活プログラムに参加。自立生活プログラムを通じ他の障害者が色々と"できる"姿を見、自分について考えたとき、自分だって同様に"できる"のではないかと勇気がわいてきた。たとえ、もし自立生活自体が自分に合わなかったとしても、少なくとも恐れずに家から出られるようになれるならしめたものだと思った。自立生活(運動)、それは本当に有効だ。自立生活は確かに人々の人生を変えていく。自己選択の出来る人間(に変えていく)。この経験を通じて、私も"どんな望みでも成しえる"ということを実感した」。ここでも自立生活センターの自立生活プログラムに参加する事で、自分が自立生活できる可能性があることに「気づき」自立生活センターの関与を通じて彼が医療モデルから「社会モデル」への思考変化を遂げていることが見て取れる。
OBTでのピア・サポートグループでのナンタの参加者への呼びかけの言葉は、障害者個人の「自己決定権の自覚」がさらに自立生活センターでの集合的な「ニーズの自覚」へと高まり、社会の環境への働きかけにいたっている事を示している。
「障害を持っている仲間が地域で暮らすためにOBTとの架け橋になるのが、自立生活センターです。何もいわずにいたら支援は必要ないと思われます。みんなで声を上げることが必要です。社会の人たちは、障害者は自分ではなにも決められないと思っているので、こういう機会に意見をまとめて伝えることが大事です」。(12月21日ボーントイOBTにて筆者、通訳、ナンタ、サンティ同席)自立生活センターのピア・サポートグループの活動は、個々人のニーズの自覚につながり、 自立生活センターとして「社会モデル」が全員に獲得されていくプロセスが観察された。
社会変化への行動が始まったか
ここでは、自立生活センターの支援を通じて本人の意識が社会モデルへと変化してきた障害者が、さらに具体的に社会変化への行動を始めたかどうかを調べたい。
12月24日、ナコンパトム自立生活センターの事務所で、専従職員Wに通訳者を通じて聞き取りを行った。
まず職員Wに、彼から見て介助サービス利用者の変化について気づいた点を尋ねた。彼は介助サービス利用者の反応について、「最初、その人の家にいったときは何もしゃべらないが、何回か介助サービスを使ううちに普通に話すようになった」と述べ、介助利用者が利用頻度を高めるに従って、自己表出するようになったことを示した。さらに職員Wは「(介助サービスを利用することにより、利用者の)自己決定の幅が広がる。一度外に出ることで今度はここに行きたいという欲求が生まれる」とも述べた。ここでは利用者は、介助サービスを通じて社会モデルの視点を持って自己決定の幅を広げ、外出するという社会参加への欲求を高めていることがわかる。
当事者が自立生活センターの支援によって社会参加するようになったことで、周囲の意識が変化する。これを自立生活センターの職員Aの例で見てみる。Aは職員であるとともに、介助サービスの利用者でもある。
近所の商店主は、Aの子供時代のことまで知っており、彼のよき友人となっている。2007年12月19日の夕刻、忙しい時間を割いて筆者・ナンタ・通訳のインタビューに応じてくれた。「自立生活センターができる3年前には、この子は本当に大丈夫なのかと思うような惨めな格好と顔つきをしていたよ。それが、今は本当に格好良いハンサムな大人になってきて、身なりも良く顔つきも明るくて自信に満ちて、全く別人のように変わってきたんだよ。おれは本当にうれしいよ」と、商店主は自分のことのように彼の変化をよろこんでくれているようだった。Aが店長から「ガールフレンドも大勢できたんじゃないか」と冷やかされると、そんなことないよと逃げ出そうとするなど、人気者になっているようだった。
この商店主は、子供時代のAが母親に負ぶわれて店に来ていたのを覚えている。3年前の彼は、惨めな格好と顔つきをしていたという。その彼の身なりが良くなり(この日はカッタシャツにジーパン姿であった)、明るくて自信に満ちた大人になったと評価している。
彼が自立生活センターの支援を受けて、自信を持って社会参加することによって、地域の人たちの障害者に対する見方が対等な人間関係を保障するものに変化している。ここでもわずかな一歩ではあるが、障害者による社会変革への行動が始まっているということがいえる。
第2節 ナコンパトム自立生活センターはいかに行政と社会を変えているか
エンパワメントした障害者は、どのようにして社会変革をしていくのであろうか。この節では、仮説で述べられた後段の自立生活センターは、「障害当事者のエンパワメントによりニーズを顕在化し、福祉サービスの向上を促し、社会変革につながる」に基づいて当事者ニーズが顕在化しているか、福祉サービスが向上しているか、について検証する。
当事者ニーズが顕在化しているか
自立生活センターが主催するピア・サポートグループで障害者同士の対話が行われ、そこで社会モデルに気づいた障害者はエンパワメントし、自らの地域社会に対するニーズを表出し始めた経過を、観察と聞き取りから調べる。
2007年12月21日の午前と午後にかけて、ピア・サポートグループを見学した。これはプッタモントンの自立生活センターが開催したもので、ナコンパトムの自立生活センターのナンタなどの協力を得て、ボーントイOBTを会場にして行なわれた。参加者は家族を含めて23名であった。
ナンタによると、OBTと話し合って、日を設定して50名の障害者登録された人に手紙を出して内26人が参加した。食費と交通費をプッタモントンの自立生活センターが支援した。参加者のうち7名は自立生活センターを全く知らず、他もほぼどんな活動をしているか知らず、中には家族にお昼も出るし、交通費も出るので行ってくればといわれてきたという人もいた。[7]
ナンタの挨拶に続いて、OBTの高齢障害担当サミノンラッタナー氏から次のような挨拶があった。「ナコンパトム自立生活センターと協力することで、地域の障害者により近い活動ができると期待している。障害者は家族の中で快適に暮らせない状況のなかにあり、支援してくれている団体があるのはうれしい。地域の人びとが助け合うべきである。また行政も多くの手助けができればいい。」
このようにOBTの全面的な協力を得て、この集会は開催された。
最初にナンタから、次の質問が参加者全員に出された。
・障害とはどういうものか、
・家族との関係
・地域の人との関係
・OBTをどう思うか
午前中は4つの問いに対して、3グループに分かれて議論が進められた。
第1の問いでは、障害というものは社会の障害者に対する配慮の欠如から起こるものであるという社会モデルの障害者観が伝えられた。この点について皆で対話しながら考えた。第2、第3の問いでは、家族や地域の中でどのような事で今困っているかが話しあわれた。
午後の議論は模造紙に書いてすすめられた。参加者の意見の中でOBTへの要望となるものを初めて全員で文章にまとめあげた。以下の項目が参加者から出されたOBTへの要望である。
・障害年金を値上げして欲しい。
・福祉制度が十分ではない。
・病院と公的機関への移動手段が欲しい
・家庭での介助や外出時の介助がほしい。
・障害者の居場所が欲しい。
・OBTの建物のアクセスが悪い。トイレを改造し広くして欲しい。
・通学支援が欲しい。
・障害者をもつ家庭への支援が欲しい。
・障害児用の車椅子が欲しい。
・手帳交付を断らないで欲しい。
・OBTはもっと地域に出て行ってニーズを聞いて欲しい。
・障害者を支援する障害者団体を支援して欲しい。
自立生活センターではこの要望を要望書にまとめ、村長に提出した。行政に自分たちのニーズを伝えていく活動は重要であり、すぐに全ての要望がかなえられることはないが、行政の補助が出て建物のアクセスが改善されたり、OBTの車を使っての移動手段の提供などが始まったりする事から、ニーズが顕在化することは社会変革の第一歩といえる。
OBTでの自立生活センターの活動を見てきたが、行政に関わることによって自立生活センターはどのように変化してきたかについてナンタは次のように語っている。「ナコンパトム自立生活センターでは40のOBTですでにピア・サポートグループを開催し、その都度村長と面会しグループ開催のお知らせと支援のお願いをしてきた。40のOBTのうち15~20が自立生活センターに好意的であり介助サービスについての支援を受けられる可能性がある」
。[8]
ナコンパトムにおいて、自立生活センターは行政との協同活動により、地域の障害者のニーズを確実に顕在化させていることがわかった
福祉サービスが向上しているか
タイにおいても2005年にTIL(タイ自立生活センター協議会)が設立され、その政治的窓口を通して2006年に自立生活運動に関する7項目要求書をタイ人間安全保障省に提出している。
ソウソウポウからのナコムパドムとプッタモントン自立生活センターへの運営補助金は、2007年10月より始まり2009年5月現在継続されている。2009年5月27日来日したタイ人間安全保障省のフンニ局長によると、「現在ではノンタブリ自立生活センター、パタヤ自立生活センターの他合計10ヶ所の地域障害者支援活動に出されている」という。この補助金制度は2007年の「障害者エンパワメント法」第23条に規定された「障害者の生活の向上と発展のための基金」[9]より拠出されている。
また同法第20条には「障害者は以下に述べる福祉と支援を含む公的な便宜を利用し、提供される権利がある」と述べられており、その第10項には「障害者の介助者は委員会の規定によりサービス料の割引と減免を受けることができる」、「介助者のいない障害者は公的機関の提供する住宅と介助の提供を受けることができる」とあり、公的介助サービスと住宅サービスが明確に規定されている。
フンニ局長によると、「一日6時間を上限として介助サービス制度をスタートさせようとしており、ノンタブリ自立生活センターの所長ティラユットに政府の障害者介助制度検討委員会の委員として入ってもらっている」という。(2009年4月27日、来日時にヒューマンケア協会事務局にて筆者聞き取り)
タイの自立生活センターによってエンパワメントした障害者達は、地域で介助を受けて暮らしていきたいというニーズを社会に顕在化させ、OBTへの要望活動から初め、ソウソウボウの補助制度に繋げ、それが障害者エンパワメント法の20条となって実り、2002年のナコンパトム自立生活センターのスタート以来7年かけて、福祉サービスの向上を現実のものにしつつある。
ナコンパトムでは、当事者のエンパワメントを通じて、ニーズを顕在化させ、福祉サービスの向上をうながし、政府の法律を変え、具体的な介助サービス制度を成立させるという社会変革のプロセスにまで至っていることが、インタビューを中心にした調査によって確認された。
第6章 考察と結論
第4章と5章を通じて、第2章9節でたてた仮説である「途上国においても重度障害者が中心になって運営される自立生活センターが成立しうること、そしてそれを基盤として、障害当事者のエンパワメントによりニーズを顕在化し、福祉サービスの向上を促し、社会変革につながること」が、ナコンパトムの自立生活センターの分析から例証された。
第1節 ナコンパトム自立生活センターの相対的独自性について
本論第2章第6節で、「途上国では自立生活センターが難しい」という疑問に触れた。またタイ国内でも、ナコンパトム以外の2つの自立生活センターでは十分に成功していない。本章ではこれらの点について、ナコンパトムにおいてはどのようなプロセスで自立生活センターが可能になったのか、その経験の相対化を試みたい。最後にナコンパトムセンターの限界についても触れておきたい。
途上国では自立生活センターが難しいと言われていたのにナコンパトムではなぜできたのか
ナコンパトムでは、どのようなプロセスで、自立生活センターが作られたのかを再び整理しておく。
第1に四肢麻痺で常時介助が必要な重度障害者であるティラワットが、ナコンパトム自立生活センターの代表をしていることである。それが親亡き後の地域での自立生活を目指す多くの障害者の要求と繋がり、自立生活センターが設立される基盤となった。
第2にティラワットが要求運動型の従来の障害者運動に限界を感じたちょうどそのときに、APCDにおける日本人講師の自立生活運動についての研修会に参加したことである。そこで彼が、サービス提供と運動体を一体化した自立生活運動に強い関心を持ったことがきっかけとなり、それが周囲の障害者に影響を及ぼし、自立生活センター設立につながった。
第3に事務局長のナンタ、プッタモントン自立生活センターの所長のサンティ共に、自立生活運動の骨格となるピア・カウンセリングに深い関心を持ち、日本における長期の研修の機会にも恵まれたために、ナコンパトムで独自のピア・カウンセリングセミナーやピア・サポートセミナーを開催できる能力を備えた。
第4に一時は貧困と家族の虐待で自殺未遂にまで追い込まれていた職員のAがピア・カウンセリングをうけて、父親との関係を改善し、自立した個人として、他の障害者の支援をするような職員として育成された事である。Aに触発され、その他のピア・カウンセラーであるC、K、Oなども、積極的に地域の障害者の家を尋ね、自立生活運動の理念を伝え、社会変化への運動へと繋げる端緒を作ったことも自立生活センター成功の要素となっている。
第5に代表のティラワットやサンティ、ナンタなどのリーダーが、全員のニーズを集約化し、OBTや地域行政や国に伝えていく的確な運動性を備えていたことである。これらが、自立生活センターを成功に導いた経過とその要素である。
生活費や住宅のない途上国の障害者にとって、自立生活は遠い先の目標でしかないのであろうか。実は、基盤整備が整えられたとしても、それを活用して自立生活へ向かうということは、自然に起こる帰結ではない。その過程ではピア・カウンセリングによるエンパワメントがなければ、親元から離れてあえて困難な自立生活へ挑むものはいない。ここでは、政治的・運動的な側面からの解釈が必要である。
途上国に限らず、多くの障害者は、社会を改革して生活の基盤整備を政府に政策的に実行させることは無理だ、と通常思っている。しかし介助サービスは、介助を使っての生活実態を地域に作り出すことによって、行政はその現実の生活実態を尊重せざるをえなくなる、という政治的意味を持つ。自立生活センターが存在しなければそのような生活実態は顕在化することはなかったわけである。いったんナコンパトム町という特定の場所に、AやBという特定の障害者が、モデル事業とはいえ、政府関連機関の補助をえて生活実態を築きあげた場合に、その支援期間が終了したからといって介助サービスがストップしてAやBが死ぬことがあれば、行政責任を問われることは必須である。これが政治的な判断を生んで国や市レベルでのサービスの継続を促すことになる。
また運動的な側面からいえば、個人としては社会を変えられないと思っていた障害者が、ピア・サポートグループを形成して、地道な活動を続けることによって、タンボンからピア・カウンセリングプログラム実施への支援金が出るような事態が実際に起こった。自分たちの行動は社会を変えられる可能性があると、障害者自身が思ってもおかしくはない。障害者が変わることによって、Aの親が自立生活センターの存在を認め、その積み重ねによって村長Wが自立生活センターの存在を有効とみるようになった。障害者が介助者を使って社会参加することを社会が認めていくことによって、国も自立生活センターの有効性を認め、介助サービスに今つなげようとしている現実がある(第5章2節)。
こうした政治的・運動的な循環を始動させるのに必要な初期条件を、上の第1から第5に述べたような人材育成の面で、ナコンパトムセンターは備えていた、というのが、ナコンパトムで自立生活センターが可能となった理由である。
ナコンパトム以外のタイの自立生活センターでは成功していないのは何故か
まず、ノンタブリとチョンブリの自立生活センターにおいては、ピア・カウンセリングが十分に行われていないために、個人のエンパワメントが不十分であった。したがって社会モデルによる障害理解が進んでいない。つまり権利としての福祉サービスへの運動が、地域の生活に根ざしたものになっていない。これが弱点としてあげられるだろう。
第2にノンタブリにおいては、自立生活センターの代表がトッポンからティラユットに交代しているが、両者共に警察と軍隊の幹部候補生養成大学卒業のエリートであり、同僚に政府高官が多い。その政治力をもって国のリハビリテーション法や障害者エンパワメント法を成立させるのに大きな力を発揮しているが、その地域での個々の障害者のニーズに根ざした運動を形成しきれていない。そのためにナコンパトム自立生活センターのようにソウソウポウからの自立生活センターへの補助金を当初から得ることができなかった。法律の実施に向けての寄与において、ナコンパトムは常に先頭を走ってきている。
チョンブリの自立生活センターではレデンプトリスト障害者職業学校の教師たちがリーダーとなっており、ナコンパトムと並ぶ有能なメンバーを揃えたセンターと言える。しかし彼らは日常的な介助を必要としない比較的軽度の四肢麻痺者である。ナコンパトムの最重度障害者は独身で、かつ収入源もチョンブリのメンバーのようにはない。日常生活の生活費にも困窮する状況で始まっているのであった。そのために、後へは引けない運動の強さを持っている。この点がナコンパトムセンターの他に比べた強みとなった。
ただし他のセンターが、弱点と限界を持つとはいえ、活動を開始している意味は大きい。もしもタイに自立生活センターがナコンパトムだけしかないとすれば、政府は介助サービスの制度化へは乗り出さなかったはずである。それは日本においても10ヶ所の自立生活センターが設立された段階で、全国自立生活センター協議会を設立し、日本政府への交渉窓口として介助サービスについての交渉をやってきた歴史がある。それからみても、タイの政府が地方の一障害者組織の活動をベースとして制度・政策を作ることは一般的には考えられないであろう。しかし幸いなことにタイにおいても、自立生活センターが全国に広まりそうな機運が見られ、2007年にTIL[10](タイ自立生活センター協議会)が設立され、その政治的窓口を通して2008年に自立生活運動に関する7項目要求書をタイ人間安全保障省に提出している。この中には自立生活センターへの運営資金の補助と、障害者介助サービスの制度化を要求した項目があり、運動の側面からみれば3年かけて運動が実り、制度化が成功したと言える。
ナコンパトム自立生活センターでは何ができていないのか
まず一人暮らしの重度障害者はまだ生み出せていない。これは介助サービスが一人暮らしの生活を支えるものとまではなってはいないことと、その継続性・持続性についての不安をセンター職員だけでなく、利用者も家族も抱いている点にある。障害者エンパワメント法の実施が決定したとしても、一日のサービス時間の上限が設定されればそれ以上の時間数の介助サービスが必要な人は暮らせないことになる。制度の運用の面で自立生活センターの運動が行政をどこまで動かせるかが今後の自立生活運動の鍵となる。
例え介助サービスが制度化されたとしても、生活費や住宅費用について今後どうするのかという問いはある。この点についてノンタブリで以前見学した障害者村と言われる場所では、10人前後の障害者が小さな家を借り、そこに木製のスロープなどの改造を行い、車いすで生活している姿を見た。質の高い住宅でなければ誰でも障害者が借りることは可能である。障害者村の人たちの場合はそれぞれ仕事を持っており、一定の収入があったが、ナコンパトムの重度障害者は一般の就労形態では雇用される可能性のない人たちである。この点では日本の自立生活センターの所長や事務局長はすべて最重度障害者であり、同じような状況にある。このような障害者が生活していくためには、自立生活センターの介助サービスが国の制度となり、その収益が生活費となることは唯一の収入の道と考えられる。
ナコンパトムのセンターの運営費については現在ソウソウポウから事務所家賃と職員人件費、介助サービス費用などが出されているが、これもこの補助制度が止まれば運営継続は困難になる。これまでは個人の持ち出しや、描いた絵の売り上げなどを使って事務所家賃を支払い、一人か二人の介助担当職員を雇用していた。今後継続的な運営を行うには、国の介助サービス料に自立生活センターの運営費が見込まれる必要がある。先進国の自立生活センターの運営経費は介助サービスの中からと、自立生活プログラム、ピア・カウンセリング、自立生活体験室、リフト移送サービスなどのサービスを市民に向けて提供するという名目で行政からの補助を受けている。ナコンパトムでもそのような方式がとられれば、今後の安定的な運営への可能性は高まる。
第2節 今後の課題
本論文で課題として残ったことについて最後に述べる。
第1に、タイの1 自立生活センターのみを対象とする調査研究にとどめたため、タイにおける他の自立生活センターとの比較検討が十分にできなかったことである。更にいえばフィリピンなど他のアジアの開発途上国における自立生活センターの分析が行われていないため、途上国の最貧困層である障害者から発する自立生活運動が社会のサービスとシステムを変えていくプロセスが十分に解明されていないところがある。今後この点についての研究を進めていきたい。
第2に、障害当事者中心でないCBRなどの開発事例と、自立生活センターを通じた開発との違いいが検討されていない。この点についても、今後必要に応じて研究していきたい。
本稿は、参加型開発に成功したモデルがあまり無いといわれる中で、当事者自身が主体者となって成功した開発の事例分析として、今後、他の開発への影響があるだろう。そして何より、この論文が途上国の障害者にとってその人生を変え、社会を変えていく端緒になれば幸いである。
参考文献
日本語文献
石井米雄(1995)『タイ仏教入門』めこん
上野千鶴子・中西正司『ニーズ中心の社会へ-当事者主権の次世代福祉戦略』2008、医学書院
小國和子(2006)『村落開発支援は誰のためか』明石書店
柿崎一郎(2007)『物語タイの歴史-微笑の国の真実』中央公論新社
川田英樹(2007)『アジア太平洋障害者センタープロジェクト(APCDプロジェクト) ケーススタディ作成に向けた現地調査結果報告書』
セン、アマルティア(1999)池本幸生、野上裕生、佐藤仁訳『不平等の再検討-潜在能力と自由』岩波書店
久野研二・中西由起子(2004)『リハビリテーション国際協力入門』三輪書店
佐藤郁哉(2002)『フィールドワークの技法 - 問いを育てる、仮説をきたえる』新曜社
立岩・安積・岡安・尾中編著(1995)『生の技法―家と施設を出て暮らす障害者の社会学』増補改訂版, 藤原書店
チェンバース、ロバート(1995)穂積智夫、甲斐田万智子(監訳)『第三世界の農村開発:貧困の解決―私たちにできる事』明石書店
中西正司編(1991)『自立生活への衝撃―アメリカ自立生活センターの組織・運営・財務』ヒューマンケア協会
中西正司(2006)「重度障害者」p34-40、『人間の安全保障を踏まえた障害分野の取り組み-国際協力の現状と課題-』FASID国際開発高等開発機構、
中西正司・上野千鶴子(2003)『当事者主権』岩波新書
中西由紀子(1996)『アジアの障害者』現代書館
中西由起子(2008)「途上国自立生活運動発展の可能性に関する考察」森壮也編『障害と開発――途上国の障害当事者と社会』IDE-JETRO
アジア経済研究所
野田直人(2007)「参加型アプローチの実際」穂坂光彦(編著)『開発基礎論Ⅲ』日本福祉大学通信大学院国際社会開発研究科
萩原康生(2006)「アジア各国の社会福祉・社会保障の制度政策③タイ」萩原康生(編著)『アジアの社会福祉』放送大学
ヒューマンケア協会(2002)「障害者の自立生活研修計画総合報告書」JICA
ヒューマンケア協会(2003)「障害者の自立生活研修計画総合報告書」JICA
ヒューマンケア協会(2004)「障害者の自立生活研修計画総合報告書」JICA
ヒューマンケア協会(2005)「障害者の自立生活研修計画総合報告書」JICA
Frieden, Lex, Laurel Richards, Jean Cole, and David Bailey (1979)
A Technical Assistance Manual on Independent Living. Huston:
The Institute on Rehabilitation and Research, 1979 (中西正司編『自立生活への衝撃―アメリカ自立生活センターの組織・運営・財務』ヒューマンケア協会
, 1991, p5 にて引用)
フレイレ、パウロ(1979)小沢有作(訳)『被抑圧者の教育学』亜紀書房
フレイレ、パウロ(1982)里見実、楠原彰、桧垣良子(訳)『伝達か対話か―関係変革の教育学』亜紀書房
外国語文献
Daly, M ed. (2001) Care Work: Quest for Security. Geneva:
International Labour Office.
DeJong, Gerben (1979) "Independent Living: From Social Management
to Analytic Paradigm," Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation, (60).
Wyatt, David K. (2003) Thailand: A Short History. Yale
University Press.
[註]
1 ヒューマンケア協会とは、1986年に東京都八王子に設立された日本で始めての自立生活センターである。ここで作られた自立生活プログラム、ピア・カウンセリングプログラム、介助サービスシステムなどが、全国とアジア各国に広がっている。
2 APCDとは、2004年に日本政府の無償供与によってバンコクにつくられた障害当事者のための研修センターである。
3 障害者登録制度:1991年の障害者リハビリテーション法、第14条で「同法で述べられた福祉サービスやリハビリテーションを受けることを望む障害者は、中央登録センターもしくは居住する県の公共福祉事務所で登録を行わなければならない」と定められた。
登録をする際には、①医師による障害を証明する診断書、②国民IDカードなどの身分証明書(未成年の場合は出生証明書)、③住民登録証明、④写真2枚、の4点が必要である(関明水「タイにおける障害者リハビリテーション―Community
Based Rehabilitationの現在と今後」、一橋大学大学院社会学研究科提出修士論文、2000年参照
4 田中紗和子「タイ農村部における障害児支援について-ナコンシータマラート県特殊教育
センターでの取り組みを事例に-」、東洋英和女学院大学大学院国際協力研究科提出修士論文、2008参照、http://www.asiadisability.com/~yuki/Theses3.html、2009年5月13日閲覧)
5 DPIとは、Disabled Peoples' Internationalのことで、世界120ヶ国に支部がある障害者団体である。障害種別を越えた世界的な障害者団体として、国連に登録されている唯一の団体である。権利擁護活動、国連での活動などを行う
6 ソウソウポウとは、社会保障と人間の安全保障省の「第3次障害者の生活の質の開発に関する国家計画2007-2011年」の「あらゆるタイプと程度の障害者の自立生活のための社会支援システムに関するプロジェクト」等を推進する外郭機関。
7 ピア・カウンセリングを研修中の障害者が、集いあってピア・カウンセリングをすることで、お互いにエンパワメントをし合いながらピア・カウンセリングの知識を深めるとともに、ストレスの解消を図ったり、共通に抱える課題について解決策を交換し合ったりするグループカウンセリング。
8 2007年12月19日のナンタへのインタビュー
9 National Office for Empowerment of Persons with Disabilities(障害者エンパワメント事務局)は2007年「障害者エンパワメント法Persons
with Disabilities Empowerment ACT.2007」を障害者との数年の協議のうえで策定した.
10タイ自立生活センター協議会は、ナコンパトム、チョンブリ、ノンタブリの3自立生活センターが2007年に設立したもので、2ヶ月に1回程度の代表者会議を行い、各センターの現状報告と政府への自立生活センターへの運営資金の要望や介助サービスの制度化を求めて活動している。2009年現在会長はチョンブリ自立生活センターの代表ウドムチョクが務めている。